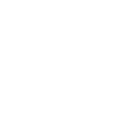感染症内科|国立病院機構熊本医療センター
部門紹介 > 診療部
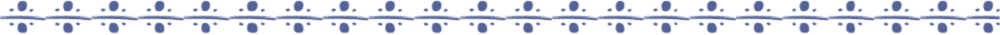
感染症内科
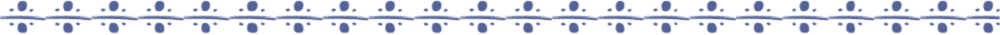
感染症内科部長あいさつ

感染症内科は当初、2017年より呼吸器内科診療と並走する形で感染症診療・教育活動を開始いたしました。特に抗菌薬治療に関する院内全科からのコンサルテーション対応を軸に、一般感染症、術後感染症、臨床各科の特異的感染症から結核(活動性・潜在性)、非結核性抗酸菌症、梅毒、日本海裂頭条虫症、重症熱性血小板減少症候群、輸入感染症としてデング熱や狂犬病疑い等の特殊な感染症診療まで行ってまいりました。
また、院内感染対策チーム(ICT)活動、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)活動等にも積極的に取り組んでいます。さらに当院は蟻田功名誉院長より30年以上の長きに渡り継続している国際協力機構(JICA)とコラボレーションした国際医療協力活動を行っており、2017年からは当科主導で厚労省・外務省、大学、国立感染症研究所等の感染症専門研究機関、地方研究所・保健所等と連携した多大なるご協力のもと、下記のような課題別研修を東京・熊本で継続しております。
そして2020年初頭からの2年間に渡るコロナ禍におきましては、ダイアモンドプリンセス号下船客ならびにクルーの診療支援を皮切りとしまして、当院内におけるCOVID-19診療システムの構築や検査体制の確立に取り組み、集中治療室(ICU)における人工呼吸管理を要する重症COVID-19診療を担当主科として救急科、多職種ICUチームと共に推進してまいりました。さらに同じ国立病院機構関連施設でのセミナー開催や診療支援を行い、東京コロナ診療臨時医療施設等でのコロナ診療支援の継続、NHO新型コロナウイルス感染症等対策研修事業における動画コンテンツ作成を継続するなど院外においても積極的にCOVID-19診療・教育活動を行っております。
今後は呼吸器内科診療を継続・拡充しつつ、一般感染症診療、幅広いCOVID-19診療、COVID-19後遺症診療、感染対策業務活動、感染症分野における国際医療協力活動を推進し、引き続き広く皆様の健康に寄与できればと考えております。
感染症内科部長 国際医療協力室長 小野宏
歴史
2017年1月1日 感染症科診療開始
2018年3月1日 日本感染症学会連携研修施設、日本感染症学会暫定指導医 取得(熊本大学呼吸器内科と連携)
2019年4月1日 感染症科から感染症内科に改名
2019年11月1日 国際医療協力室から国際医療協力センターに改名
最近の国際医療協力活動
2017年9月 重症感染症などのアウトブレイク対応強化のための実地疫学(管理者向け)
研修生:アフリカ諸国+フィリピン(合計9か国、14名)
2019年2月 重症感染症などのアウトブレイク対応強化のための実地疫学(管理者向け)
研修生:アフリカ諸国+パラオ(合計5か国、8名)
2019年11月 重症感染症などのアウトブレイク対応強化のための実地疫学(管理者向け)
研修生:アフリカ諸国+中国(合計9か国、11名)
2020年2月 ダイアモンドプリンセス号下船者のCOVID-19診療支援
※その他に米国内科学会日本支部HPPC: Health and Public Policy Committee業務を推進しております。
上記ボランティア活動等を評価され、米国内科学会日本支部よりACPJC Volunteerism Award 2021を受賞いたしました。
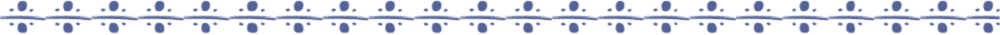
診療内容・特色
当科では呼吸器内科診療と感染症内科診療、救急・集中治療を組み合わせた統合的集学的呼吸器感染症診療の実践・推進を目指しております。所属スタッフは1名体制ですが、外来診療におきまして呼吸器診療全般ならびに一般感染症内科診療(HIV診療・渡航外来診療を除く)を行っています。入院診療の主力としましては呼吸器感染症診療全般、細菌・ウイルス感染症を契機とした間質性肺炎急性増悪・COPD増悪、各種敗血症等の重症病態管理ですが、2021年4月から2023年3月までは重症COVID-19診療を重点的に担当主科として担っておりました。2024年4月よりはコロナ禍以前の体制に戻りつつあります。
当科は院内各科のみならず、日本全国の諸施設と連携を図りつつ診療に当たっています。更に、WHOの天然痘撲滅プロジェクトリーダーであり、1980年に天然痘撲滅宣言を行った蟻田功名誉院長より受け継がれる国際医療協力活動を継承し、JICAとの協力体制のもとで課題別研修を開催してきました。その他、米国からJeffery A. Hagen先生を当院にお招きし、“Dr. Hagen’s round”と題した北米型レジデント研修のプログラミングとファシリテーションを行うなど、多方面での業務を同時に推進しております。(2024.4現在、JICA課題別研修ならびに北米型レジデント研修は中止中)
ご案内
感染症診療は単一科で診療することは頗る困難であり、呼吸器診療・研究等のバックグラウンドを活かしつつ、当科・小児科(小児感染症、ウイルス感染症)・皮膚科(皮膚感染症)・血液内科(HIV)とで連携体制を組み、さらに臨床各科や薬剤部・細菌検査室との密接な連携を介した集学的感染症診療を行います。
皆様の日々の診療でお困りの感染症患者様を含め、随時ご相談くださいませ。ご紹介の際には事前に診断に必要な検体培養(喀痰、尿、便、血液等:結核を疑う厚い隔壁の空洞性病変等を認める場合には喀痰抗酸菌培養)をご提出お願いいたします。またCOVID-19症例につきましては重症患者様の入院診療を中心に対応しており、現時点で中等症以下の診療は原則行っておりません。COVID-19罹患を疑う症状を有する患者様をご紹介いただく場合には、大変お手数ですが事前の抗原検査(定性・定量)やPCR検査等のご施行ならびにそれら陰性確認のほどよろしくお願い申し上げます。尚、COVID-19罹患後の患者様におけます各種後遺症症状(Long COVID)につきましては当方にて診療を承りますのでご相談くださいませ。その他、麻疹・水痘・結核などの空気感染を来す疾患を疑う場合、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)等特別な感染対策を要する疾患を疑われる場合等には事前にご相談くださいませ。
尚、当方は現時点で1名体制の診療科であり、やむなく診療制限を行う可能性がございますのでご承知おきください。また、当院は第一種・第二種感染症医療機関ではなく、成人を中心とした診療を行っておりますので、疾患やその特性、患者年齢によりましては適宜各診療科・各感染症専門医療機関等へのご紹介を頂きますよう宜しくお願いいたします。
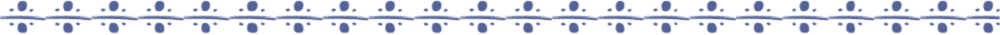
医療設備
感染症内科診察室2室/呼吸器内科診察室1室 (うち陰圧室)2室
入院陰圧室8床 ICU(COVID-19対応時:重症5床まで対応)
MALDI Biotyper (BRUKER、検査室)
GeneXpert(Beckman Coulter、検査室)
FilmArray(BioFire Diagnostics、検査室)
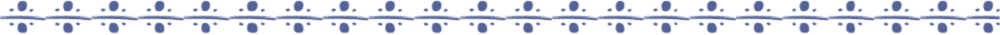
症例数・治療・成績
当科は抗菌薬を用いた治療方針決定や特殊病態の診断に関する院内コンサルテーション(併診依頼を含め150-200件/年)に迅速対応しております。
外来診療は2023年度統計で月平均72.0名の外来診療を行い、新患は月平均3.9名でした。
入院診療は呼吸器感染症領域(誤嚥性肺炎を含む肺炎、間質性肺炎やCOPDに合併する二次性肺炎あるいはそれら増悪、粟粒結核など特殊肺炎まで:集中治療を要する重症例を含む)と共に、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)やデング熱などの西日本特有の疾患や旅行者感染症等各種感染症疾患診療を対応しております。これまで重症COVID-19診療を担当主科として集中治療を継続してきましたが、2021.4-2024.4期の統計では合計51例(挿管・人工呼吸器症例34例、非挿管症例(NPPV/HFNC等)17例)を担当し、各救命率はそれぞれ85.3%、94.1% (total 88.2%))でした。その他、各科併診での各重症度のCOVID-19診療やクラスター対応も行いました。(上記統計にはICU以外での当科診療患者は含みません)
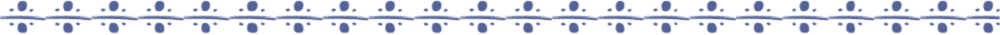
スタッフ紹介
職名 氏名 免許取得年 | 専門医 所属学会 など | 専門分野 |
感染症内科部長 呼吸器内科医長 国際医療協力センター長 オノ ヒロシ 小野 宏 平成13年 | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医・指導医 日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医 日本感染症学会感染症専門医 米国内科学会(ACP)フェロー(FACP) 米国胸部疾患学会(ACCP)フェロー(FCCP) 米国癌研究学会(AACR)正会員 日本呼吸器学会推薦インフェクションコントロールドクター(ICD) 医学博士(東京医科歯科大学統合呼吸器病学) | 呼吸器疾患 感染症疾患 内科疾患一般 COVID-19 国際医療協力 |
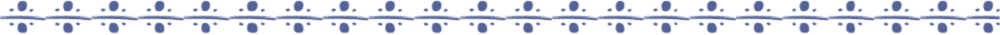
今後の目標・展望
感染症内科・呼吸器内科一般診療に加えまして、呼吸器感染症を中心に重症COVID-19を含む各科重症感染症等の診療を勇んで取り組んでまいります。今後、睡眠診療を含め呼吸器内科分野業務をも含めた外来・入院業務を順次拡大予定です。そして、過去3年間のコロナ禍で実行困難な状況にありました当院の伝統である国際医療協力活動を可能な限り推進してまいります。更に、積極的な米国内科学会活動等を通じて医のプロフェッショナリズムの観点から多くの提案を継続し、引き続き国際貢献を推進してまいります。今後とも皆様からの温かいご支援、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。