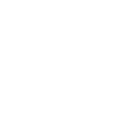研究情報公開(研究166~)|臨床研究部|国立病院機構熊本医療センター
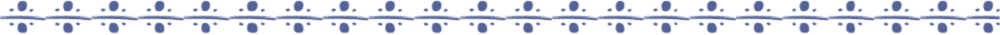
研究情報公開(オプトアウト)
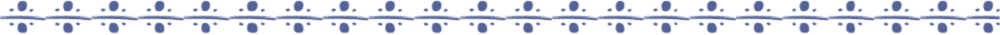
研究166~
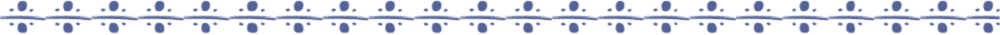
213.脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究
Close The Gap-Stroke J-ASPECT Study
研究の概要
当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、日常診療で得られた以下の診療情報を研究データとしてまとめるものです。研究のために、新たな検査などは行いません。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方で、ご質問がある場合、またはこの研究に診療情報を使ってほしくないとのご意思がある場合は、遠慮なく下記の担当者までご連絡<ださい。お申出による不利益は一切ありません。ただし、すでに解析を終了している場合には、研究データから情報を削除できない場合がありますので、ご了承ください。
研究の目的
本研究の目標は、
1)我が国の診療実態に適合し、かつ国際比較が可能な、脳卒中を含む循環器疾患の医療の質を的確に計測しうるQIを開発・評価すること
2)策定したQIに基づく適切なベンチマーキングの手法を開発・評価すること
3)未整備な回復期リハビリテーションや維持期の介護・廃用症候群防止等の標準的治療の確立に資するQIを策定すること
4)本邦の脳卒中、急性循環器疾患の救急搬送の実態を検証すること
5)脳卒中の予後の改善に向けたボトルネックがどこに存在するか
を、継続的に検討するフィードバックを行うことを目標とします。QIの評価に関しては、アウトカム指標(入院中の死亡率など)に対するプロセス指標(QIの遵守率)の影響を、ロジスティックモデルにより解析します。
対象となる方
2020年4月1日~2022年3月31日の間に急性期脳梗塞を発症し、t-PA静注療法、血栓回収療法を実施された方
利用する診療情報
診療清報上の主傷病名、入院契機傷病名、もしくは診療報酬明細書上の傷病名、年齢、性別、入院日、既往歴、脳卒中に関連した診療行為及び時間経過、予後など。本研究の研究内容、参加施設名、患者さん向けの資料などにつきましては、研究班ホームページ (J-ASPECT Study)にて随時公開しております。
外部機関への研究データの提供
上記の診療情報を、次の研究機関と共有して、共同で研究を進めます。取得された診療情報を業務委託先である健康保険医療情報総合研究所(PRRISM)で集積し、必要な情報を抽出した解析用データセットを作成し、研究責任者および分担研究者に配布いたします。
提供先機関の名称
国立循環器病研究センター 循環器病統合情報センター
研究責任者の氏名
国立循環器病研究センター 病院長 飯原弘二
研究実施期間
研究許可日より2024年4月30日まで(予定)
個人情報の取り扱い
お名前、住所などの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。この研究の成果を発表したり、それを元に特許等の申請をしたりする場合にも、個人が特定できる情報を使用することはありません。
本研究で得られた臨床情報およびその抽出ロジックを将来、脳卒中や循環器疾患の研究のために二次利用する場合や、研究計画書を変更する場合があります。その場合は、研究倫理審査委員会での審議を経て研究統括管理責任者の許可を受けて実施されます。同意取得の手続きとしては、オプトアウトの機会を設ける場合などがあります。オプトアウト文書は国立循環器病研究センター公式サイトの『実施中の臨床研究』のページに公開いたします。
研究代表者
国立循環器病研究センター 病院長 飯原弘二
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 脳神経外科 中川隆志
問い合わせ先
国立循環器病研究センター 病院長 飯原弘二 電話06-6170-1069(代表)
国立病院機構熊本医療センター脳神経外科部長 中川隆志 電話096-353-6501(代表)
ホームページ
*J-ASPEC丁研究
本研究の研究内容、参加施設名、患者さん向けの資料などにつきましては、研究班ホームページ (J-ASPECT Study)にて随時公開しております。
212.当院における二重特異性抗体製剤によるサイトカイン放出症候群の発生状況に関する調査
研究の概要
体内のさまざまな部位でがんのもとになる異常細胞が発生することがあります。体内の免疫は、このようながん細胞など本来体の中にあるべきでないものを見つけると攻撃して排除します。この免疫機能の中心的な役割をリンパ球であるT細胞がおこなっています。
二重特異性抗体療法は、がん細胞にT細胞を誘導することで、がん細胞を攻撃する新しい治療方法です。しかし、ニ重特異性抗体療法は、高頻度にサイトカイン放出症候群(Cytokine Release Syndrome:以下CRS)が発症することが報告されています。
CRSは、T細胞による過剰な免疫反応によって起こります。多くの場合は、軽度または中等度の発熱、悪心・悪寒、筋肉痛といったインフルエンザのような症状ですが、一部の患者さんでは、重度の低血圧、頻脈、呼吸困難などによって急激に進展し、亡くなることがあります。二重特異性抗体療法を安全に行うために、CRS発現時の対処方法を確立する必要があります。
そこで、当院で二重特異性抗体製剤であるブリナツモマブによる治療を受けた患者さんの診療情報(カルテの記録内容)を参考にデータを収集し、二重特異性抗体製剤の安全性を評価するとともに今後のCRS発現時対処方法について検討を行います。
研究の目的と方法
本研究の目的は、二重特異性抗体療法によるCRS発現時の対処方法を明確にすることです。平成30(西暦2018)年11月から令和5(西暦2023)年12月までの間に当院でプリナツモマブを投与開始した患者さんを対象とし、診療で得られた臨床データ(年齢、性別、診断名、病歴、治療歴、体重、身長、薬剤投与墓、副作用歴、CRS発症日、併用療法、併用薬、前投薬の有無、バイタルサイン、臨床検査値(WBC、Neut、Hb、PLT、AST、ALT、LD、Bil、Ser、 Ccr、Na、K、Cl、P、Ca、フェリチン、CRP、PT、APTT、INR、フィブリノーゲン、IgG)を電子カルテから集計・分析を行う後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者様に新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究に扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究対象者(患者様)の個人情報(氏名、住所、電話番号、カルテ番号など)は記載せず、対応表を作成して管理しますので、個人情報は特定されません。
実施期間
研究対象期間:平成30(西暦2018)年11月1日~令和5(西暦2023)年12月31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和7(西暦2025)年3月31日まで
研究成果の発表
調査した患者様のデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者様のデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 治験管理室 宮本 聖子
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 治験管理室 宮本 聖子
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 治験管理室 宮本 聖子
電話:096·353-6501
211.A病院におけるrapid response system: RRS の効果の検討
このたび当院では、上記の医学系研究を、国立病院機構熊本医療センター倫理委員会の承認・許可のもと、倫理指針及び法令を遵守して実施します。
今回の研究では、同意取得が困難な対象となる患者様へ向けて、情報を公開しております。なおこの研究を実施することによる、患者様への新たな負担は一切ありません。また患者様のプライバシー保護については最善を尽くします。
本研究への協力を望まれない患者様の旨を「8 お問い合わせ」に示しました連絡先までお申し出下さいますようお願いいたします。
研究組織
国立病院機構熊本医療センター
本研究の目的、方法 目的:
当院では、2022年4月から迅速対応システム(Rapid response system :RRS)を開始し、2022年7月から早期警戒スコア(National Early Warning Score :NEWS)と病棟からのコールの二重に起動基準を導入し、24時間365日の体制で迅速対応チーム(Rapid response team :RRT)が状態変化した患者様に対応しています。すでに先行研究により、RRSの効果として心停止の減少が発表されていますが、当院において、どのような効果が得られているか解析することで、今後のRRSの課題を明確化することができ、新たな知見を得ることができると考えています。
方法:入院患者のNEWS及びバイタルサインの状況,RRT介入件数の推移,院内緊急コール(ドクターハート)の発生数,院内緊急コール対応症例の6-8時間前のNEWS,院内急変によりICUに入室した患者様のICU滞在日数と生存退院率をR version 4.3.1を使用し、それぞれの関連性について解析を行う予定です。解析に必要なデータは、すべて暗号化されたUSBメモリーで保存し、鍵のかかる医療安全管理室内の机の引き出し内で厳重に管理します。
研究責任者
所属 国立病院機構熊本医療センター 看護部長室 甲斐彰
問い合わせ先
本研究に関する質問や確認、研究協力の拒否は、下記へご連絡下さい。
氏名:甲斐 彰
連絡先
国立病院機構熊本医療センター 医療安全管理室
電話:096−353−6501 内線:5505
Mail:kai.akira.dn@mail.hosp.go.jp
210.原因不明の発熱症例から感染性心内膜炎の可能性を見積もる予測モデルの再構築と検証正
研究の概要
感染性心内膜炎(IE)は、発熱を来す疾患で呼吸不全、四肢麻痺、関節痛など様々な症状を呈します。身体所見や検査所見が非特異的であることから、診断困難となることが多いです。診断が遅れると予後不良となるため早期診断が重要です。近年、IEの後ろ向き研究から作成されたIE予測モデルが報告され、その有用性はある程度確認されましたが、問題点も指摘されました。そのため、多施設前向き研究での新たなIE予測モデルの再構築ならびにすでに作成されたIE予測モデルの検証が必要となりました。今回、原因不明の発熱症例からIEの可能性を見積もる予測モデルの再構築と検証を行うために佐賀大学医学部付属病院地域医療教育研究センターが中心となり、多施設前向き研究が提案され、国立病院機構熊本医療センターも参加することといたしました。
研究の目的と方法
今回の研究は、原因不明の発熱症例からIEの可能性を見積もる予測モデルの再構築と検証を行うことを目的とします。本研究は、18の医療機関(佐賀大学医学部付属病院、岡山大学病院、順天堂大学、東邦大学医療センター大森病院、獨協医科大学病院、聖マリアンナ医科大学病院、国立病院機構熊本医療センター、練馬光が丘病院、明石医療センター、宮崎県立宮崎病院、亀田総合病院、飯塚病院、足利赤十字病院、国立病院機構嬉野医療センター、筑波大学水戸地域医療教育センター・水戸協同病院、浦添総合病院、聖隷浜松病院、社会医療法人祐愛会織田病院)の総合診療部門におけるIEの予測モデルの再構築および検証するための前向き症例対照研究です。本研究では、2024年4月1日~2025年5月31日に国立病院機構熊本医療センター(救急外来もしは総合診療科)を受診された患者さんのうち、37度以上の発熱を来した18歳以上の方、発熱の原因が特定されない状態で入院された方、感染性心内膜炎疑いで入院された方、感染性心内膜炎と確定診断されて入院された方を対象としています。入院前に惑染性心内膜炎以外の発熱の原因が特定できた方、入院前に血液・尿検査・胸部レントゲン検査の一つ以上が末施行である方、前医を含め入院48時間以降に発熱を来した方、本研究への参加に同意されなかった方、担当者が研究への参加が不適当と判断した方は除外いたします。全体の目標症例は、300名です。日常診療で得られたデータを電子カルテから抽出いたします。抽出したデータをもとにIEの予測モデルの再構築と検証、固有弁または生体弁症例における予測モデルの感度分析、先行研究で開発されたIE予測モデルの検証を統計学的手法を用いて行います。データの解析は、研究責任者(山下駿)が中心となって行います。
本研究の参加について
これにより、患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせまでこ連絡ください。
調査する内容
本研究は、新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究対象者(患者さん)の個人情報(氏名、住所、電話番号、カルテ番号など)は、記載せず、対応表を作成して管理しますので、個人情報は特定されません。
実施期間
調査対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日
研究期間:倫理委員会承認後~2027年3月31日
研究成果の発表
研究代表者は、研究終了後、遅滞なく研究精査を学会や学術論文で発表いたします。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
佐賀大学医学部地域医療科学教育研究センター 山下駿
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター総合診療科 國友耕太郎、辻隆宏
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター総合診療科 國友耕太郎、辻隆宏
電話:096-353-6501
209.急性心筋梗塞における患者来院から心カテ室入室までの救急外来看護師の行動分析
研究の概要
当院では救急外来に検査処置チームが設置されており、救急で来院した急性心筋梗塞患者の初期対応~心臓カテーテル検査・治療の介助までを、日勤帯・夜勤帯関係なく全て救急外来看護師が担っています。
2020年4月1日~2021年3月31日までの、急性心筋梗塞患者来院~心カテ室入室までにかかった時間を調査したところ、中央値30分という結果になりました。この所要時間は、他病院と比較すると短く、急性心筋梗塞の患者の治療においてdoor-to-balloon timeを短縮することに繋がり、患者の予後に深く影響すると考えます。そのために、救急外来看護師が、ホットラインでの事前情報入手~心カテ室入室までの、救急外来看護師による良質な看護実践や時間短縮に関する思考過程について言語化されたプロセスが必要だと考え、救急外来で勤務されている看護師の皆様ヘインタビューをさせていただきたいと思います。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、このインタビュー調査にご協力をいただけますようお願い申し上げます。
研究目的
ホットラインを受けてからの救急外来看護師の思考過程や行動が、心カテ室入室までの時間短縮にどのような影響を与えているのかを明らかにすることを目的としています。
今後、救急外来において心カテ室入室までの介助に携わる看護師が、的確に・迅速に対応することができるよう、教育に役立たせ、さらに心カテ室入室までの時間短縮を目標とし、患者にとって有益な看護を提供することができると考えています。
研究対象者
インタビュー調査に協力していただきたい方は、救急外来に勤務する看護師の皆様16名です。
研究方法
インタビューでは、ホットラインでの事前情報を受けてから心カテ室入室までの看護実践と思考過程についてお聞きします。
インタビューは半構造化面接法を用いて、業務時間内に20分程度、個室で行います。研究への参加の同意が得られた方には、研究者が日程調整を行い、インタビュー調査をさせていただきます。許可を得られた場合のみ、調査内容を録音させていただきたいと思います。
研究期間
この調査は、2024年1月~2月で実施します。
倫理的配慮
本研究への協力は、研究協力者の自由意思に甚づくものであり、同意しない場合もいかなる不利益を被ることはありません。本研究はインタビューを予定しており、ICレコーダーを使用します。研究期間中は、研究に使用するデータは研究者が厳重に管理し、録音内容は一定期間保存の後、速やかに削除します。また、研究終了後文書で残したデータに関しても一定期間保存の後、速やかにシュレッダーにて破棄します、インタビューで得た情報は、外部へ漏らさないこと、個人情報・プライバシーを徹底致します。
本研究開始時に研究の趣旨を文書と口頭で説明しますので、同意書の記入をお願いいたします。研究に同意した後でも、いつでも同意を撤回することができます。その際は、同意書撤回所を用います。同意を撤回したい場合は研究者へご連絡ください。
また、研究への参加・不参加・撤回、いずれの場合でも個人への業績への影響は全くありません。
プライバシー保護に関して
研究協力者ご自身のプライバシーに関することはすべて匿名とし、秘密を厳守します。個人を識別する情報は一切使用しません。
研究結果の公表について
研究結果は論文としてまとめ、看護関連学会で発表させていただく予定です。また、研究のデータ及び結果は研究目的以外には使用することはありません。
お忙しいところ、皆様の貴重な時間に、研究にご協力いただくことは大変恐縮ではありま すが、何卒研究の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
この研究についてのご質問・ご意見がございましたら、研究責任者へいつでもお尋ねください。
研究責任者
熊本医療センター 救命救急センター看護師 東坂悠紀
共同研究者
救命救急センター病棟師長 深川千晶 渡辺純也 村山公栄 今村祐太
問い合わせ先
救命救急センター病棟師長 深川千晶
208.肝細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害薬と血管新生阻害薬併用療法(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)ならびに複合免疫チェックポイント阻害薬(トレメリムマブ+デュルバルマブ)の治療効果および有害事象に関する研究
《研究対象者》
2020年12月より国立病院機構熊本医療センターにおいてテセントリク+アバスチン(アテゾ
リズマブ+ベバシズマブ)治療またはトレメリムマブ+デュルバルマブ(イミフィンジ+イジュ
ド)治療を受けた患者様
研究協力のお願い
この研究は、国立病院機構熊本医療センターでテセントリク+アバスチン(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)治療またはトレメリムマブ+デュルバルマブ(イミフィンジ+イジュド)治療を受けた患者様の治療効果と有害事象(副作用)を解析することにより、患者様に病状に応じた最適な医療を提供することを目指すためのものです。
情報等の使用について、直接に説明して同意はいただかずに、このお知らせをもって研究に関する事項を公開いたします。対象となる方におかれましては、研究の主旨・方法をご理解いただきますようお願い申し上げます。
この研究への参加を希望されない場合、あるいは、研究に関するご質問は下記の問い合わせ先へご連絡ください。
研究目的および方法
(研究の目的について)
2020年9月より切除不能肝細胞癌の一次治療として保険診療可能となった免疫チェックポイント阻害薬と血管新生阻害薬併用療法(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)ならびに複合免疫チェックポイント阻害薬(トレメリムマブ+デュルバルマブ)による治療はこれまでのソラフェニブやレンバチニブをはじめとする分子標的薬に比べ生存期間の延長や腫瘍の縮小効果において高い治療効果を示しています。一方、副作用として、これまでの分子標的薬にない免疫原性有害事象(irAE/imAE)の発現が起こることも判っています。当院では2020年12月より切除不能肝細胞癌に対して本治療を行っていますが、自施設での症例に対して臨床的解析を行い、治療効果と有害事象を明らかにすることを目的とします。
(研究の方法について)
当院の電子カルテシステムから画像検査および検体検査(血液および尿検査)項目を抽出し、匿名化された状態でデータベースを構築し、各種解析を行います。研究期間は 2020年12月1日~2030年11月30日です。
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター:電話番号096-353-6501 消化器内科
研究責任者
杉 和洋
207.肝細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害薬と血管新生阻害薬併用療法(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)の治療効果および有害事象に関する研究
《研究対象者》
2020年12月より国立病院機構熊本医療センターにおいてテセントリク+アバスチン(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)治療を受けた患者様
研究協力のお願い
この研究は、国立病院機構熊本医療センターでテセントリク+アバスチン(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)治療を受けた患者様の治療効果と有害事象(副作用)を解析することにより、患者様に病状に応じた最適な医療を提供することを目指すためのものです。
情報等の使用について、直接に説明して同意はいただかずに、このお知らせをもって研究に関する事項を公開いたします。対象となる方におかれましては、研究の主旨・方法をご理解いただきますようお願い申し上げます。
この研究への参加を希望されない場合、あるいは、研究に関するご質問は下記の問い合わせ先へご連絡ください。
研究目的および方法
(研究の目的について)
2020年9月より切除不能肝細胞癌の一次治療として保険診療可能となった免疫チェックポイント阻害薬と血管新生阻害薬併用療法(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)はこれまでのソラフェニブやレンバチニブをはじめとする分子標的薬に比べ生存期間の延長や腫瘍の縮小効果において高い治療効果を示しています。一方、副作用として、これまでの分子標的薬にない免疫原性有害事象(irAE)の発現が起こることも判っています(IMbrave150試験)。当院では2020年12月より切除不能肝細胞癌に対して本治療を行っていますが、自施設での症例に対して臨床的解析を行い、治療効果と有害事象を明らかにすることを目的とします。
(研究の方法について)
当院の電子カルテシステムから画像検査および検体検査(血液および尿検査)項目を抽出し、匿名化された状態でデータベースを構築し、各種解析を行います。研究期間は 2020年12月1日~2023年11月30日です。
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター:電話番号096-353-6501 消化器内科
研究責任者
杉 和洋
206.成人T細胞白血病(ATL)に対する同種移植後の予後に移植前モガムリズマブ投与が与える影響に関する研究
熊本医療センターで成人T細胞白血病・リンパ腫に対して同種造血幹細胞移植の治療を受けた患者様
( 生命科学・医学系研究に関する情報 )
当院では、以下の生命科学・医学系研究を実施しております。生命科学・医学系研究とは、従来の臨床研究、疫学研究、ヒトゲノム・遺伝子解析研究を含み、人を対象として国民の健康の保持増進、患者様の傷病からの回復、生活の質の向上に資する知識を得る等を目的とする研究のことです。この研究は、通常の診療で得られた過去の診療記録等をまとめる研究です。このような研究は、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定により、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究について詳しくお知りになりたい時や、研究への参加を希望されない場合は下記の「お問い合わせ先」へご連絡ください。
研究の目的
ATLは、通常化学療法のみでは極めて予後不良であり、近年、移植可能年齢の患者に対して同種移植が施行されています。しかし非寛解例への移植の予後は依然厳しいです。本邦においてはATLに対して世界に先んじて2012年からモガムリズマブが保険適応となっていますが、2013年までの症例でモガムリズマブの移植前使用で重症移植片対宿主病(GVHD)が増加したことが報告されているため、移植前の使用には注意が彩要です。また、この報告時には最終のモガムリズマブ投与から移植までの期間が50日未満の例で有意に非再発死亡率が高く、その結果全生存率も劣るということから実臨床においては50日は間隔を空ける例が増えていると予想されます。しかし、50日以上経過した場合にもやはり依然としてGVHD増加のリスクがある可能性はありますが、前回の解析の段階では移植前モガムリズマブ使用症例数が限られており解析は困難でした。上述の通り現在は50日以上問隔を空けている症例が多いと予想され、50日以上間隔を空けた例での解析をより詳細に行えるものと期待できます。このように移植前モガムリズマブ使用に関しての情報が新たに得られることで、実臨床における移植前のモガムリズマブ使用を検討する際の参者となることが期待できます。
研究の方法
移植学会のデータベースに含まれる情報に加えて二次調査を行った上で移植前のモガムリズマブ投与に関連する情報を調蓋した上で、解析を行います。この研究のために新たに患者様に追加で負担をお願いして行うものではありません。
対象となる患者様
2016年1月1日から2019年12月31日までに成人T細胞白血病リンパ腫と診断され、同種造血幹細胞移植の治療を受けた患者様を対象にしています。
試料や診療録(カルテ)から利用する情報
個人情報が公表されることはいかなる形でもありません。後方視的に過去の診療録を調査する際には、個人情報が特定されないやり方で情報を収集します。
個人情報が特定されない情報を研究責任者機関にて管理し、統計学的解析を行います。
情報の提供を行う機関の名称及びその長の氏名
大阪国際がんセンター 総長 松浦 成昭
本研究全体の研究代表者
大阪国際がんセンター 血液内科 藤 重夫
当院の研究責任者
(研究機関名)(研究責任者の所属・氏名)
国立病院機熊本医療センター 血液内科 河北 敏郎
研究組織
この研究が行われる研究機関と研究責任者は次に示すとおりです。
施設担当者 施設・診療科名
荒 隆英 北海道大学病院 血液内科
大西 康 東北大学病院 血液内科
勝岡 優奈 国立病院機構仙台医療センター 血液内科
神田 善伸 自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科
堺田 恵美子 千葉大学医学部附属病院 血液内科
奈良 美保 秋田大学医学部附属病院輸血細胞治療・移植再生医療センター
福島 健太郎 大阪大学 血液・腫瘍内科学
寺倉 精太郎 名古屋大学医学部附属病院 血液内科
田代 晴子 帝京大学医学部附属病院
池田 宇次 静岡県立静岡がんセンター 血液・幹細胞移植科
諫田 淳也 京都大学医学部附属病院 血液内科
烏野 隆博 りんくう総合医療センター 血液内科
松岡 賢市 岡山大学 血液・腫瘍内科
徳永 雅仁 今村総合病院
吉満 誠 鹿児島大学病院 血液・膠原病内科
森内 幸美 佐世保市総合医療センター 血液内科
神田 善伸 自治医科大学附属病院 血液科
緒方 正男 大分大学医学部 血液内科
河北 敏郎 国立病院機構熊本医療センター
太田 秀一 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院
衛藤 徹也 浜の町病院 血液内科
渡邊 光正 兵庫県立尼崎総合医療センター
角南 一貴 国立病院機構岡山医療センター 血液内科
田中 正嗣 神奈川県立がんセンター 血液・腫瘍内科
中邑 幸伸 山口大学医学部附属病院 第三内科
高山 信之 杏林大学医学部付属病院 血液内科
遠藤 慎也 熊本大学病院血液内科
皆 日承 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター血液・細胞治療科
糸永 英弘 長崎大学病院 血液内科
小野田 昌弘 千葉市立青葉病院 血液内科
赤坂 尚司 天理よろづ相談所病院 血液内科
高橋 勉 島根大学医学部附属病院 血液内科
狩俣かおり ハートライフ病院 血液内科
花本 仁 近畿大学奈良病院 血液内科
大渡 五月 鹿児島医療センター 血液内科
森 康雄 九州大学病院 血液・腫瘍・心血管内科
小宅 達郎 岩手医科大学 血液腫瘍内科
梅澤 佳央 東京医科歯科大学病院 血液内科
北野 俊行 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 血液内科
堤 豊 市立函館病院 血液内科
但馬 史人 国立病院機構米子医療センター 血液腫瘍内科
澤 正史 安城更生病院 血液・腫瘍内科
上田 恭典 倉敷中央病院 血液内科
近藤 忠一 神戸市立医療センター中央市民病院 血液内科
鬼塚 真仁 東海大学医学部 血液腫瘍内科
高瀬 謙 九州医療センター 血液内科
福田 隆浩 国立がん研究センター中央病院 造血幹細胞移植科
西田 徹也 日赤愛知医療センター名古屋第一病院
小宅 達郎 岩手医科大学附属病院 血液腫瘍内科
萩原 真紀 横浜市立大学附属病院 血液リウマチ感染症内科
堤 豊 市立函館病院 血液内科
横山 洋紀 東京慈恵会医科大学 腫瘍・血液内科
高橋 勉 島根大学医学部附属病院 血液内科
伊藤 満 京都市立病院 血液内科
服部 憲路 昭和大学病院 血液内科
佐伯 恭昌 愛媛県立中央病院 血液内科
吉本 五ー 佐賀県医療センター好生館
南口仁志 滋賀医科大学医学部附属病院 無菌治療部/血液内科
飯田 真介 名古屋市立大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学
森島 聡子 琉球大学病院 第二内科
柴田 悠平 岐阜市民病院 血液内科
伊野 和子 三重大学医学部附属病院 血液内科
兼村 信宏 岐阜大学医学部附属病院 血液・感染症内科
倉橋 信悟 豊橋市民病院 血液・腫瘍内科
牧山 純也 佐世保市総合医療センター 血液内科
木村 文彦 防衛医科大学校病院 血液内科
河野 徳明 県立宮崎病院 内科
中前 博久 大阪公立大学医学部附属病院 血液内科・造血細胞移植科
上村 智彦 原三信病院 血液内科
個人情報の取り扱いについて
研究で使用する診療情報は、患者様の氏名や生年月日など、患者様を直接特定できる個人情報を特定の個人を識別することができないように加工します。また、研究成果は学会や学術雑誌などで発表することがありますが、その際も患者様を特定できる情報は使用しません。
研究の資金源等、関係機関との関係について
本研究の二次調査のデータ収集/管理に関しては、日本造血 免疫細胞療法学会(JSTCT)から日本造血細胞移植データセンターCJDCHCT)への業務委託費により賄われます。
参加を希望しない患者様へ
この研究に参加を希望されない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。あなたに関するデータを削除します。ただし、学術発表などすでに公開された後のデータなど、患者様またはご家族からの撤回の内容に従った措置を講じることが困難となる場合があります。
問い合わせ先
国立病院機熊本医療センター 血液内科 河北 敏郎
〒860-0008 熊本市中央区二の丸1-5
TEL : 096-353-6501
205.胸部X線画像病変検出ソフトウェアに関する検討
研究の概要
近年、AI技術の進歩は目覚ましく、医療分野でも画像診断支援を中心とした業務支援への活用が進みつつある。富士フイルム社製の胸部X線画像病変検出ソフトウェアであるCXR-AIDは、ディープラーニング技術を使ったAIによる胸部X線画像診断支援ソフトウェアであり、胸部X線画像の結節・腫瘤影、浸潤影、気胸が疑われる領域を自動的に検出、マーキングする。解析結果は、病変の確信度に応じてヒートマップ(カラー)表示され、確信度の最大値がスコアとして画像内に表示される。CXR-AIDは、医師の読影をサポートするツールとして期待されているが、先行文献が少なく、臨床に関しての詳細な情報が少ない。
本研究では、CXR-AIDの病変検出能や特性を理解するため、CXR-AIDの解析結果とcomputed tomography (CT)の読影所見の比較をおこなう。
研究の目的と方法
対象:救急外来で胸部ポータブル撮影とCT撮影を同日におこなった患者様
方法:CXR-AIDの解析結果とCTの読影所見の比較をおこなう。
本研究の参加について
本研究により、患者様に新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な画像データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使用しないで欲しいと希望される方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、令和5年10月1日~令和5年12月31日に国立病院機構熊本医療センター救急科にて、同日に胸部ポータブル撮影とCT撮影をおこなった患者様を対象としております。新たに試料や情報を取得することなく、既存のCXR-AID解析結果とCT画像および読影所見を用いて実施する研究です。
実施期間
研究対象期間:倫理委員会承認後~令和 6 年 3 月 31 日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 6 年 6 月 30 日まで
研究成果の発表
調査した患者様のデータは、集団として分析し、学会や論文で発表いたします。また、個々の患者様のデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構 熊本医療センター 放射線科 診療放射線技師 木原 聡
当院における研究責任者
国立病院機構 熊本医療センター 放射線科 診療放射線技師 木原 聡
問い合わせ先
国立病院機構 熊本医療センター 放射線科 診療放射線技師 木原 聡
電話番号:096-353-6501(代表)
204.重症COVID-19患者における栄養投与量と経腸栄養プロトコルに関する研究
研究の概要
重症の患者様における治療支援として、「日本版重症患者の栄養療法ガイドライン2016」に沿った栄養療法を行うことが求められています。重症の患者様へ経腸栄養プロトコルを使用することで、経腸栄養を早期に開始でき、投与エネルギー量・たんぱく質量が増加するという報告があります。しかし、重症COVID-19患者様において、エネルギー25kcal/kg/dayを達成する因子として、経腸栄養プロトコル使用の有用性は不明です。また、経腸栄養プロトコルの使用と血圧低下や胃排液量増加などの有害事象の頻度との関連についても不明です。
本研究の目的は、重症COVID-19患者様においてエネルギー25kcal/kg/dayを達成する因子として、経腸栄養プロトコル使用の有用性を明らかにすることです。また、経腸栄養プロトコルの使用と有害事象の発生頻度の違いを明らかにすることです。
研究の目的と方法
本研究の目的は、重症COVID-19患者さんの経腸栄養プロトコルと栄養量達成因子の関連について検討することです。日常診療で得られた臨床データ(年齢、性別、身体所見や生化学検査など)を電子カルテから集計・統計分析を行う後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、令和2年4月1日~令和5年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センターに入院し人工呼吸管理を施行した患者さんを対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究終了後の収集したデータは、鍵をかけたファイルにて5年間保管ののち、破棄いたします。
実施期間
研究対象期間:令和2年 4月 1日~令和 5年 3月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 7年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室
熊本大学大学院 医学教育部 医学専攻 外科系 臨床国際協力学講座 加來正之
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
電話:096-353-6501
203.妊娠糖尿病患者における妊娠中の体重変化量と産後耐糖能及び周産期合併症の関連
研究の概要
妊娠糖尿病は、母体における出産後の糖尿病発症や、母体・児における周産期合併症発症のリスク因子であり、妊娠中の血糖コントロールを含めた母体管理は、これらの予防に重要とされております。低出生体重児頻度が多い本邦において、2021年に妊娠中の体重増加目安量が引き上げられましたが、妊娠糖尿病患者に新基準を適用した場合の産後耐糖能異常及び周産期合併症発症に及ぼす影響については不明であります。そのため、本研究では、妊娠糖尿病患者における妊娠中の体重変化量と産後耐糖能及び周産期合併症の関連性について検討します。
研究の目的と方法
本研究の目的は、妊娠糖尿病患者さんの妊娠中の体重変化量と産後耐糖能及び周産期合併症の関連性について検討することです。糖尿病・内分泌内科外来初診時及び産後受診時に診療で得られた臨床データ(臨床所見、検査所見など)を集計し統計分析を行う後方視的研究です。
本研究の参加について
本研究に参加することで、患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを使わないで欲しいと希望される場合や、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、平成30年4月1日~令和5年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科外来を受診し産前血糖管理を行い、産後に75g経口ブドウ糖負荷試験を実施した妊娠糖尿病患者さん約1,000例を対象としています。診療で得られた臨床データを集計し統計分析を行う研究です。
実施期間
研究対象期間:平成30年 4月 1日~令和 5年 3月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後 ~令和 10年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表する時に、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 / 国立大学法人熊本大学大学院 医学教育部 山下晶穗
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 / 国立大学法人熊本大学大学院 医学教育部 山下晶穗
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 山下晶穗
電話:096-353-6501
202.妊娠糖尿病患者における若年期からの体重変化量と産後耐糖能及び周産期合併症の関連
研究の概要
妊娠糖尿病は、母体における出産後の糖尿病発症や、母体・児における周産期合併症発症のリスク因子であり、妊娠中の血糖コントロールを含めた母体管理は、これらの予防に重要とされております。しかし、本邦の妊娠糖尿病患者における若年期からの体重変化量と産後耐糖能異常及び周産期合併症発症に関する報告はありません。そのため、本研究では、妊娠糖尿病患者における若年期からの体重変化量と産後耐糖能及び周産期合併症の関連性について検討します。
研究の目的と方法
本研究の目的は、妊娠糖尿病患者さんの若年期からの体重変化量と産後耐糖能及び周産期合併症の関連性について検討することです。糖尿病・内分泌内科外来初診時及び産後受診時に診療で得られた臨床データ(臨床所見、検査所見など)を集計し統計分析を行う後方視的研究です。
本研究の参加について
本研究に参加することで、患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを使わないで欲しいと希望される場合や、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、平成30年4月1日~令和5年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センター糖尿病・内分泌内科外来を受診し産前血糖管理を行い、産後に75g経口ブドウ糖負荷試験を実施した妊娠糖尿病患者さん約1,000例を対象としています。診療で得られた臨床データを集計し統計分析を行う研究です。
実施期間
研究対象期間:平成30年 4月 1日~令和 5年 3月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後 ~令和 10年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表する時に、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 / 国立大学法人熊本大学大学院 医学教育部 山下晶穗
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 / 国立大学法人熊本大学大学院 医学教育部 山下晶穗
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 山下晶穗
電話:096-353-6501
201.精神疾患・認知症患者に対する急性期精神科病棟での転倒防止の検討についての研究
研究の概要
この研究は、患者様の安全・安楽かつ快適な入院生活を援助する目的で、精神疾患・認知症を患った急性期精神病棟での転倒事例を通し、患者様の疾患や症状、状況を明らかにし転棟件数減少に向け実態調査を行い、今後の看護援助に役立てていきたいと考えています。
研究の目的と方法
目的:入院中に転倒された状況を医療安全報告書、診療録より情報を収集し調査することにより実態を明らかにし、転倒件数減少に向けた看護に繋げて行く事を目的としています。
方法:転倒の要因として考えられる項目として年齢・既往歴・入院日数・生活自立度・環境・薬剤・精神状態について医療安全報告書、診療録より情報を収集し分析させていただきます。
本研究の参加について
研究目的や主義、方法等について院内ホームページにて研究情報公開を行っています。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がある際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。ただし学会発表後や論文報告後は集計から外すことは不可能となります。
調査する内容
本研究は、令和3年4月1日~令和5年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センター7南病棟に入院し療養中に転倒された患者様を対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存のカルテ情報・医療安全報告書を用いて実施する研究です。終了後は破棄いたします。
調査期間
研究期間:倫理委員会承認後~令和6年3月31日まで
実施期間:倫理委員会承認後~令和5年11月30日まで(データ収集期間)
研究成果の発表
調査した患者様のデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者様のデータをする際も、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構医療センター 7南病棟 看護師 池尻幸大郎
当院における研究責任者
国立病院機構医療センター 7南病棟 看護師長 松本広美
問い合わせ先
国立病院機構医療センター 7南病棟 看護師長 松本広美
電話:096-353-6501
200.疫学調査「口腔がん登録
研究の概要
2016年に全国がん登録が開始されているが、口腔がんに特化した項目は極めて少ない。また頭頸部悪性腫瘍全国登録が行われているが、対象臓器が広く、調査すべき医療機関をすべてカバーしきれていないなど調査が行き届いていないのが現状である。
また、口腔は解剖学的・生理学的に特殊な部位であり、他の頭頸部がんとまとめるには問題が多いため、口腔がんに特化した調査研究が必要である。
研究の目的と方法
①口腔がん登録によりデータを集積して、症例数、治療内容、生存率等の基礎データを計測し、日本における口腔がん医療の評価・発展に役立てる
②将来の口腔がん研究のための基礎的資料とする
③全世界的口腔がん情報との比較を可能とするため
本研究の参加について
本研究はこれまで一部の口腔外科診療施設で実施していたが、この度実施体制を拡大し、准研修施設にも適応となった。当院は口腔外科学会の指定する准研修施設であり、本研究に参加する。
なお、ご自身のデータを本研究に使わないでほしいと希望される方、その他、研究に関して質問がございます際は、末尾の問い合わせ先にご連絡ください。
調査する内容
2018年1月1日以降に共同研究機関で口腔がんと診断された患者。
利用する診療情報は、性別、診断時年齢、来院経緯、重複がんの有無および内容、喫煙、飲酒、アルコールに対する反応性、慢性的刺激の有無、緑黄色野菜摂取、診断日、初発/多発、発生部位、側性、病理組織診断名、進展度(TNM分類)・病期、治療の有無、治療態度、治療内容、原発巣の再建の有無、pN分類、経過観察結果、最終経過観察日または死亡日。これらをカルテで確認していく。
研究対象件数 全体5000例/年 の予定である。
調査期間
実施場所:熊本医療センター歯科口腔外科
研究対象期間:平成30年1月1日~令和9年12月31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和9年12月31日まで
研究成果の発表
本研究は学会が継続的に行う事業であり、総括責任機関が5年ごとに調査の継続を判断し研究機関の更新を行う。
研究責任者は研究の進捗状況を1年に1回関連学会に公表する。
研究代表者
栗田 浩
所属 口腔がん登録委員会委員長、信州大学医学部医学科歯科口腔外科学
職名 教授
当院における研究責任者
谷口 広祐
所属 国立病院機構熊本医療センター歯科口腔外科
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター歯科口腔外科 谷口広祐
096-353-6501(代表)
199.当院における切除不能及び転移性腎細胞癌に対する薬物療法の治療効果と安全性についての検討
研究の概要
切除不能及び転移性腎細胞癌(mRCC)の1次治療および2次治療以降の薬物療法として免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬の併用療法、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法、免疫チェックポイント阻害薬単独療法、分子標的薬単独療法などが推奨されています。そこでその患者背景、治療効果、生存率、有害事象、臨床検査所見等の結果により切除不能及びmRCCに対する1次治療および2次治療以降の薬物療法の有用性、有害事象の対処法、治療パターン及び逐次療法の詳細を明らかにする。
・当院を受診され切除不能及び転移性腎細胞癌と診断され、1次治療および2次治療以降の薬物療法を受けられた患者様の背景、臨床検査結果、治療効果、有害事象、生存率等を調査します。
・本研究は当院のみの研究であり当院泌尿器科にて情報を集計、解析し、今後の切除不能及び転移性腎細胞癌に対する薬物療法の研究に役立てます。
研究の目的と方法
•目的
切除不能及び転移性腎細胞癌(mRCC)の1次治療および2次治療以降の薬物療法を施行した患者の背景情報及び臨床特性、治療効果、生存率、有害事象を明らかにする。治療ライン別の切除不能及びmRCCに対する実臨床の治療パターン及びレジメンの順序を明らかにする。
•方法
切除不能及び転移性腎細胞癌患者様で2018年11月から2024年3月の間に1次治療および2次治療以降の薬物療法を開始する方を対象にカルテを利用して、治療前の患者背景、病理組織所見、画像所見、採血所見、治療後の治療パターン、有害事象、採血所見、画像所見、生存率、治療効果などの情報を使用します。情報は、匿名化し誰の情報かわからないようにした上で暗号化し、集計、解析します。
本研究の参加について
該当する患者様の電子カルテ上の情報を当方で集計させて頂きます。通常の切除不能及び転移性腎細胞癌に対する治療同意書に電子カルテを利用した情報収集および集計、解析、学会発表、論文報告についての可能性については記載してありそれを用いて同意取得を行っております。そのため改めて同意書を頂いたりすることもございません。また、御参加の御意志を改めて確認することもございません。個人情報はすべて匿名化して報告させて頂きますので個人のプライパシーは守られています。万ー、この調査に参加したくない患者様がいらっしゃいましたら当方に連絡頂けますと集計からはずさせていただき、調査を中止させて頂くことが可能です。ただし論文、学会報告後は集計からはずすことは現実的に不可能になります。
調査期間
・対象となる患者様
切除不能及び転移性腎細胞癌(mRCC)の1次治療および2次治療以降の薬物 法を施行した患者様
・研究期間
2018年11月1日~2024年3月31日まで
・研究実施期間
倫理委員会承認後~2025年3月31日まで
研究成果の発表
・研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も個人を判別できるような情報は利用しません。
・研究に利用する情報は、お名前、住所など個人を判別できる情報は削除し、研究用の番号をつけます。また、研究用の番号とあなたの名前を結びつける対応表を当院の研究責任者が作成し、研究参加への同意の取り消し、診療情報との照合などの目的に使用します。対応表や個人の情報は、研究責任者が責任をもって適切に管理致します。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター泌尿器科 前田 喜寛
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター泌尿器科 前田 喜寛
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター泌尿器科 前田 喜寛
TEL:096-353-6501(病院代表)
198.当院における基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生菌による菌血症に対する抗菌薬初期選択が与える影響について
研究の概要
抗菌薬は使いすぎると耐性菌(抗菌薬が効かない細菌)を増やすことにつながります。カルバペネム系抗菌薬は、多くの種類の細菌に対して効果を現し、また、他抗菌薬に耐性となった細菌にも効果を現す薬です。近年、カルバペネム系抗菌薬に耐性となる細菌の報告もあり、そのため、適正に使用するよう厚生労働省より提言されています(AMRアクションプラン2023 - 2027)。耐性菌の1つである基質特異性拡張型βラクタマーゼ(以下、ESBL)産生菌(抗菌薬を分解する酵素を作り出す細菌)による菌血症(血液中にESBL菌が存在している状態)治療として、カルバペネム系抗菌薬が推奨されています。しかし、カルバペネム系抗菌薬以外にもESBL産生菌に抗菌力を示す抗菌薬が多数報告されています。
今回、熊本医療センター(以下、当院)外来受診時に血液培養よりESBL産生菌が検出された患者さんにおいて、臨床的特徴と治療開始時に投与された抗菌薬を調査することにより、初回に選択された抗菌薬ESBL産生菌による菌血症に対する治療効果を明らかにすることができ、抗菌薬の適正使用に貢献できると考えます。
研究の目的と方法
本研究の目的は、治療開始時の抗菌薬選択が、ESBL産生菌による菌血症の治療効果に与える影響を明らかにします。本研究の方法は、当院外来受診時の血液培養結果よりESBL産生菌が検出された患者を対象とします。日常診療で得られた臨床データ(診断名、血液培養結果、入院期間、抗菌薬投与期間、転帰、年齢、性別、身体所見や生化学検査など)を電子カルテから集計・統計分析を行う後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、令和2年4月1日~令和5年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センターに入院し当院外来受診時の血液培養からESBL産生菌が検出された患者さんを対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究終了後の収集したデータは、鍵をかけたファイルにて5年間保管ののち、破棄いたします。
調査期間
研究対象期間:令和2年4月1日~令和5年3月31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和6年3月31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも個人が特定されることはありません。
研究代表者
熊本医療センター 薬剤部 宮田拓周
当院における研究責任者
熊本医療センター 薬剤部 宮田拓周
問い合わせ先
熊本医療センター 薬剤部 宮田拓周
電話:096-353-6501
197.当院におけるエンホルツマブベドチン(パドセブ®点滴静注用30mg)による皮膚障害発現状況と患者背景について
研究の概要
エンホルツマブベドチン(以下、EV)は尿路上皮癌に対する新規抗体薬物複合体です。EVの標的であるNectin-4が皮膚に発現していることから、薬理作用に起因して皮膚障害が発現する可能性が示唆されており、治験時においても皮膚障害は高頻度で出現しています。EVによる皮膚障害のリスク因子については明らかにされていません。一般に、皮膚疾患・免疫抑制状態・高い日光曝露の既往歴を有する患者では皮膚反応が発現しやすく、肝・腎機能障害がある患者では、重度の皮膚障害が遷延化・重症化しやすいとされています。今回、当院でEVを投与した患者の皮膚障害発現状況と患者背景について調査します。本研究により、皮膚障害リスク因子を究明し、EVを安全に使用する方法が判明すると、今後の尿路上皮癌のがん化学療法における支持療法の発展に貢献できると考えます。
研究の目的と方法
EV治療開始後、皮膚障害が発現した患者の臨床的特徴を調査し、皮膚障害の発現に関連する要因を明らかにすることを目的としています。
本研究では2021年12月から2023年3月までの間に当院でEVを投与開始した患者を対象としています。診療で得られた臨床データ(疾患名、皮膚疾患の既往、白血球数、肝・腎機能、EV投与後の皮膚障害発現状況等)を電子カルテから抽出します。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究に扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究対象者(患者様)の個人情報(氏名、住所、電話番号、カルテ番号など)は記載せず、対応表を作成して管理しますので、個人情報は特定されません。
調査期間
研究対象期間:令和3年12月1日~令和5年3月31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和6年3月31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 薬剤部 松藤敬佑
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 薬剤部 松藤敬佑
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 薬剤部 松藤敬佑
TEL:096-353-6501
196.当院におけるベンダムスチン(トレアキシン®点滴静注液)10分間投与の血管痛発現状況の検討
研究の概要
悪性リンパ腫の治療に使用されるベンダムスチン点滴静注液は、従来の1時間点滴静注に加え、2022年2月に10分間点滴静注の新用法が追加となりました。熊本医療センター(以下、当院)においても、2022年6月に登録レジメンを10分間投与に切り替えを行いました。ベンダムスチンによる副作用の一つに血管痛があります。10分間投与時の安全性、忍容性を検討する第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験(2018001試験)における血管痛の発現頻度は過去の臨床試験と比較して増加していなかったものの、液剤、同一患者さんでの1時間投与と10分間投与の比較は行われていません。この比較を行うことは、10分間投与の安全性のさらなる検証につながり、安全な治療の提供に貢献できると考えます。今回、液剤1時間投与から10分間投与へ切り替えた患者さんの血管痛発現状況について調査・検討を行います。
研究の目的と方法
本研究では、2022年6月の当院登録レジメン変更時期前後(2022年1月から2022年12月まで)に、ベンダムスチン点滴静注液を投与した患者さんのうち、治療途中で1時間投与から10分間投与に変更した患者さんを対象としています。中心静脈から投与している患者さんは除外します。診療で得られた臨床データ(疾患名、治療レジメン、年齢、性別、身長、体重、ベンダムスチン投与量・希釈輸液量・投与時間、血管痛発現の有無等)を電子カルテから抽出します。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究に扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究対象者(患者さん)の個人情報(氏名、住所、電話番号、カルテ番号など)は記載せず、対応表を作成して管理しますので、個人情報は特定されません。
調査期間
研究対象期間:令和 4年 1月 1日~令和 4年 12月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 6年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 薬剤部 平池 美香子
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 薬剤部 平池 美香子
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 薬剤部 平池 美香子
TEL:096-353-6501
195.当院におけるベネトクラクス(ベネクレクスタ®)+アザシチジン(ビダーザ®)療法の使用状況と適正使用への薬剤師の関わり
研究の概要
ベネトクラクス+アザシチジン療法は2021年3月に急性骨髄性白血病に対して適応追加となった療法です。ベネトクラクスは、主にCYP3Aという代謝酵素で代謝されます。CYP3A阻害薬と併用する場合、体内からベネトクラクスの排泄が遅れる可能性があり、副作用発現頻度が増加することが考えられます。そのため、用量調節基準が設けられており、ベネトクラクス投与時は、投与量について医療スタッフの相互確認が重要となります。今回、当院において、急性骨髄性白血病患者さんのベネトクラクス使用状況を明らかにすることにより、スタッフへの確実な情報提供の実施、また薬剤師業務の標準化につながり、ベネトクラクス+アザシチジン療法の安全で継続的な適正使用へ貢献できると考えます。
研究の目的と方法
本研究は、2021年4月~2023年3月までの期間に急性骨髄性白血病に対してベネトクラクス+アザシチジン療法を開始した患者さんを対象としています。診療で得られたデータ(性別、年齢、ALT、AST、総ビリルビン値、白血球数、好中球数、血小板数、芽球数、ヘモグロビン、治療開始時点での併用薬、ベネトクラクスの用量、薬剤師の介入状況)を電子カルテにて後方視的に調査を行い分析します。
本研究の参加について
本研究により患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に取り扱います。本研究にご質問のある方、ご自身のデータを使用しないでほしいと希望される方は末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査期間
研究対象期間:令和 3年 4月 1日~令和 5年 3月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 6年 3月 31日まで
研究成果の発表
研究成果は集団として分析し、学会や論文で発表します。またこの研究成果を発表する場合、患者さん個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構 熊本医療センター 薬剤部 馬場 結子
当院における研究責任者
国立病院機構 熊本医療センター 薬剤部 馬場 結子
問い合わせ先
国立病院機構 熊本医療センター 薬剤部 馬場 結子
電話:096-353-6501(代表)
194.緩和ケア患者に適した口腔内評価ツールの検証
研究の概要
緩和ケア患者が抱く口腔疾患は、口腔乾燥、口腔カンジダ症、嚥下障害、粘膜炎など多岐にわたって報告されており、最期までQuality Of Life (QOL)を維持するためにも口腔ケアは非常に重要とされています。しかし、緩和ケア患者に対して推奨される口腔内評価ツールはなく、私たち医療従事者は、緩和ケア患者の口腔をどう評価し、介入したら良いのか漠然としたままです。
口腔内を包括的に評価するツールとしてOral Assessment Guide (OAG)とOral HealthAssessment'1bol(OHAT)があり、いずれも信頼性と妥当性が検証されている評価ツールです。これらは歯科医師に限らず誰しもが視診で評価することができ、侵襲はありません。
今回の研究で、OAGとOHATどちらの評価ツールが緩和ケア患者に適したものかが明らかとなれば、そのツールをもとに緩和ケア患者への口腔ケアのプロトコルができ、マニュアル作成へと繋げられる可能囲があります。
研究の目的と方法
緩和ケア患者にとって、Oral AssessmentGuide (OAG)とOral Health AssessmentTool (OHAT)のどちらの口腔内評価ツールが適しているか検討することを目的とします。診療で得られた臨床データを電子カルテから集計し、時間依存性ROC曲線法と機械学習などによる統計手法を用いて検証する後ろ向き研究です。
本研究の参加について
以下の対象患者に対して、過去の診察情報から調査を行います。新たに検査や情報を取得することはありません。
・対象基準
(1)令和3年3月1日~令和5年3月31日までの間に当医療センターに入院していた患者
(2)末期がんと診断された患者
(3)緩和ケアチームによる治療を受けた患者
(4)口頭・書面によるinformed consentを行い、歯科介入に同意を得た患者
・除外基準:
延命のために化学療法を受けていた患者
なお、ご自身のデータを本研究に使わないでほしいと希望される方、その他、研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先にご連絡ください。
調査する内容
以下の内容を既存の診療情報から調査します。
年齢、性別、癌の原発部位、経口摂取量、Performance Status(PS)、死亡日、OAGとOHATを用いた口腔内の評価結果、残存歯数、咬合支持域、ブラッシング回数
※OAG:
声、嚥下、口唇、舌、唾液、粘膜、歯肉、歯・義歯の8つの項目から構成。
各項目は1,2,3とスコア化され、8(正常)~24(異常)点の合計点で評価される。
※OHAT:
口唇、舌、歯肉・粘膜、唾液、残存歯、義歯、口腔清潔および歯痛の8つの項目から構成。
各項目は0,1,2とスコア化され、0(正常)~16(異常)点の合計点で評価される。
調査期間
研究対象期間:令和3年3月1日~令和5年3月31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和6年3月31日まで
研究成果の発表
海外への論文投稿や国内の学会発表を予定しています。
研究代表者
熊本医療センター 歯科口腔外科 中尾 美文
当院における研究責任者
熊本医療センター 歯科口腔外科 中尾 美文
問い合わせ先
熊本医療センター 歯科口腔外科 中尾 美文
096-353-6501(代表)
193.病院前救護における精神科救急スクリーニング&トリアージ尺度の妥当性に関する研究
研究の概要
精神心理的な問題を抱えて救急搬送される方を迅速かつ適切に搬送するための尺度について妥当性を検討します。
研究の目的と方法
精神心理的な問題がある場合、救急隊の現場活動の時間や病院照会回数が増えることが知られていますので、その改善に資する尺度を検証します。多施設共同での前向き調査で、熊本市消防局が調査協力病院へ搬送した方で、該当する方について、個人を特定しない形で調査します。
本研究の参加について
対象:2023年9月1日から2024年3月31日までの間に救急搬送された、精神系の主訴、自損行為を主訴とする患者様を対象としています。
研究方法:救急活動実施時、また、受診時に記録された診療録から、研究計画書に記載された項目について抽出し、個人を特定できないよう匿名化を行った上で、用紙に記録します。記録された用紙は厳重に管理された方法で郵送し、調査事務局に蓄積し統計解析を行います。
調査する内容
施設情報、基本情報、医療情報など。
調査期間
研究対象期間:令和 5年 9月 1日~令和 6年 3月31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 8年 3月31日まで
研究成果の発表
研究代表施設によって、第31回・第32回日本精神科救急学会学術総会などで発表します。また、研究終了時に報
告書を倫理委員会に提出します。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 精神科部長 橋本 聡
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 精神科部長 橋本 聡
問い合わせ先
対象となる患者様で、ご自身の検査結果などの研究への使用をご承諾いただけない場合や、研究についてより詳しい内容をお知りになりたい場合は、下記の問い合わせ先までこ連絡下さい。
ご協力よろしくお願い申し上げます。
研究責任者:氏名 橋本 聡
所属:国立病院機構熊本医療センター精神科部長
住所:熊本市中央区二の丸1番5号TEL: 096-353-6501(代表) 〔内線5816〕
192.日本インターベンショナルラジオロジ一学会における症例登録データベース事業
研究の概要
日本インターベンショナルラジオロジ一学会(事務局:〒355-0063 埼玉県東松山市元宿1丁目18番4号FAX: 0493-35-4236)では、本学会に参加する施設で行ったIVR診療(血管塞栓術、血管拡張術など)の情報を登録し、IVR診療の状況を把握し、各種疾患の診断冶療の向上に役立てる取り組みをlVR学会症例登録として実施しております。この事業は、現在の我が国のIVR診療の現状を浮き彫りにし、基礎と臨床の種々の研究にも貢献するものと考えられます。
当院は、上記の日本IVR学会による全国症例登録の趣旨に賛同し、登録事業に積極的に協力して参ります。当院でIVR診療を行いました患者様については、個人情報を削除した後、診療内容をIVR学会事務局に届出いたします。但し、非同意の意思表示がなされた場合には届け出をいたしません。また、後に非同意や登録の削除を申し出られた場合にも登録を削除いたします。ご不明な点などありましたら、診療科の担当医までお気軽にお尋ね下さい。
研究の目的と方法
IVRの症例情報を集計・登録することにより、我が国におけるIVR診療の現状を明らかにし、今後のIVR診療の進歩・普及を図ることを目的としています。
本研究の参加について
本研究により患者様に新たに検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究に扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、新たに試料・情報を取得することはなく、既存のカルテデータを用いて実施する研究です。研究対象者(患者様)の個人情報(氏名、住所、電話番号)は記載せず、個人情報は特定されません。
調査期間
研究対象期間:令和 5年 1月~
研究実施期間:倫理委員会承認後~ 令和10年 12月 31日まで
研究成果の発表
研究成果については、学会、論文などでの発表を予定しています
研究代表者
奈良県立医科大学附属病院 吉川 公彦
当院における研究責任者
放射線科 井上 聖二郎
問い合わせ先
放射線科 井上 聖二郎
TEL:096·353-6501
191.重症COVID-19患者における栄養療法に関する研究
研究の概要
重症COVID-19患者さんに対する栄養療法の有効性についての報告は少ないです。本研究は、栄養療法と患者さんの治療経過の関連を把握するものになります。
本邦の重症COVID-19患者さんにおいて、早期経腸栄養開始や目標栄養投与量を探ることは、治療支援のため重要な事項と考えます。
研究の目的と方法
本研究の目的は、重症COVID-19患者さんの栄養療法と生存の有無や人工呼吸管理日数などの関連について検討することです。日常診療で得られた臨床データ(年齢、性別、身体所見や生化学検査など)を電子カルテから集計・統計分析を行う後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、令和3年7月1日~令和5年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センターに入院し人工呼吸管理を施行した患者さんを対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究終了後の収集したデータは、鍵をかけたファイルにて5年間保管ののち、破棄いたします。
調査期間
研究対象期間:令和3年 7月 1日~令和 5年 3月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 7年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 / 熊本大学大学院 医学教育部 医学専攻 外科系 臨床国際協力学講座
加來正之
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
電話:096-353-6501
191.重症COVID-19患者における栄養療法に関する研究
研究の概要
重症COVID-19患者さんに対する栄養療法の有効性についての報告は少ないです。本研究は、栄養療法と患者さんの治療経過の関連を把握するものになります。
本邦の重症COVID-19患者さんにおいて、早期経腸栄養開始や目標栄養投与量を探ることは、治療支援のため重要な事項と考えます。
研究の目的と方法
本研究の目的は、重症COVID-19患者さんの栄養療法と生存の有無や人工呼吸管理日数などの関連について検討することです。日常診療で得られた臨床データ(年齢、性別、身体所見や生化学検査など)を電子カルテから集計・統計分析を行う後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、令和3年7月1日~令和5年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センターに入院し人工呼吸管理を施行した患者さんを対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究終了後の収集したデータは、鍵をかけたファイルにて5年間保管ののち、破棄いたします。
調査期間
研究対象期間:令和3年 7月 1日~令和 5年 3月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 7年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 / 熊本大学大学院 医学教育部 医学専攻 外科系 臨床国際協力学講座
加來正之
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
電話:096-353-6501
190.循環器疾患診療実態調歪(JROAD)のデータベースと二次調査に基づく致死性心室性不整脈患者の診断・治療・予後に関する研究(研究C:Brugada症候群に関する調査研究「JROAD-Brugada調査研究」)
当院に心室細動・心室頻拍・院外心停止で入院された患者さま・ご家族様へ研究へのご協力のお願い
当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、日常診療で得られた以下の診療情報を研究データとしてまとめるものであり、ご自身またはご家族の健康に関する新たな結果が得られるものではありません。また、研究のために、新たな検査などは行いません。この案内をお読みになり、ご自身またはご家族がこの研究の対象者にあたると思われる方で、ご質問がある場合、またはこの研究に診療情報を使ってほしくないとのご意思がある場合は、遠慮なく下記の担当者までご連絡ください。お申し出による不利益は一切ありません。
ただし、すでに解析を終了している場合には、研究データから情報を削除できない場合がありますので、ご了承ください。
【対象となる方】
2012年4月1日~2021年3月31日の間に、心室細動・心室頻拍・院外心停止で入院された方で、病名に「Brugada症候群」が登録されている方
【研究の目的】
Brugada症候群は、特徴的なBrugada型心電図を示し、明らかな器質的心疾患を認めず、心室細動をきたす比較的稀な病態です。発症は男性に多いことが知られ、女性での診断、治療内容、転帰に関しての全国規模の報告がありません。
本研究では、全国規模のデータベースである循環器診療実態調査(JROAD)のデータベー
スと各治療施設からの追加情報を用いて、Brugada症候群の患者さんの原因疾患、治療内 容、転帰を明らかにし、今後の早期の診断及び治療に役立てていくことを目的にしています。
【利用する診療情報】
患者背景、自覚症状、初発の致死性心室性不整脈あるいは院外心停止の診断、内服薬、血液検査、遺伝子検査、心電図関連検査、心臓カテーテル検査、心臓電気生理学的検査、心臓超音波検査、胸部レントゲン検査、胸腹部CT、心臓MRI、心臓核医学検査、心筋生検、致死性心室性不整脈に対する薬物治療および非薬物治療、退院後に患者さんに起こった出来事とその日付、新型コロナワクチン接種歴、新型コロナウイルス感染症の治療歴、病理学的検査の結果
【情報の管理責任者】
国立病院機構 熊本医療センター 循環器内科 診療部長 藤本 和輝
【研究の実施体制】
この研究は、他の施設と共同で実施されます。研究体制は以下のとおりです。
研究代表者
国立循環器病研究センター 心臓血管内科 相庭 武司共同研究機関
本書類の末尾参照
本研究で収集した情報を、下記の施設で保管し、解析を行います。提供する際は、あなたを特定できる情報は記載せず、個人が特定できないように配慮いたします。
機関名:国立循環器病研究センター
研究責任者:心臓血管内科 相庭武司連絡先:06-6170-1070
提供方法:紙媒体で情報を送付する揚合は追跡可能な郵送方法、エクセルデータで情報を送付する場合は電子メール(必要に応じてパスワードによる保護を行う)、インターネットを使用して提供する場合はセキュリティ条件を満たした「Electric Date Capture System」で提供します。
【研究期間】
研究許可日より2026年3月31日まで(予定)
【個人情報の取り扱い】
お名前、住所なとの個人を特定する情報につきましては厳重に管理を行い、学会や学術雑誌等で公表する際には、個人が特定できないような形で使用いたします。
【利益相反】
本研究の利益相反状態に関しては、各研究機関にて適切に管理されています。
利益相反についてもっと詳しくお知りになりたい方は、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。
【問合せ先】
国立病院機構熊本医療センター 循環器内科 診療部長 藤本 和輝
電話:096-353-6501(代表)
189.平成28年(2016年)熊本地震における被災地内災害拠点病院の患者状況に関する研究
研究の概要
災害医療は災害の規模や種類に応じて対応が様々であります。そのため、今までの研究は過去の災害の事例報告等に留まってしまうことが大半で、統計学的な研究はあまり行われておりません。災害時には、災害時特有の診療体制で多くの患者さんの診療を適切に行うことが大切です。平成28年(2016年)熊本地震において国立病院機構熊本医療センターを受診された患者さんの受診状況を検討し、災害時にどのような医療体制が必要かを検討します。
研究の目的と方法
災害時には、多数の患者さんが病院を受診します。病院が被災している状況で多数の患者さんの診療を円滑に行うためには、災害時に特化した診療体制が必要です。今回私たちは、平成28年(2016年)熊本地震で国立病院機構熊本医療センターを受診された患者さんのデータを調査して、災害時の医療体制に必要なことは何かを検討します。
本研究の参加について
本研究に参加することにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
患者さんの年齢、性別、病名、重症度、入院病棟、治療内容、入院期間などを電子カレテから収集します。患者さんの氏名・住所・生年月日など個人を特定する情報は調査しません。データは過去のカルテから調べるだけですので、新たな情報の聴取や採収はありません。
調査期間
実施期間:研究実施許可日(通知書発行日)より 2025年3月31日まで(調査対象期間:2016年4月)
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。データは個人が特定できない形で保存します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 救命救急・集中治療部 渋沢崇行
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 救命救急・集中治療部 渋沢崇行
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 救命救急・集中治療部 渋沢崇行 電話: 096-353-6501
188.重症COVID-19患者における予後栄養指数に関する研究
~ワクチン接種および各種治療薬が使用可能となったデルタ株・オミクロン株流行期における検討~
研究の概要
重症COVID-19患者さんに対する重症化や死亡は、性別や年齢、既往疾患など様々な因子が報告されています。その中でも日常臨床で採取できるデータを用いた簡便な計算式かつ、重症化および死亡リスクの評価指標である予後予測因子の有用性も示されています。
しかし、ワクチン接種や治療歴を含めた報告は我々が検索しうる限りありません。本研究は、ワクチン接種やCOVID-19治療薬が使用されるようなった現在において、重症化や死亡リスクとして報告されている因子の有効性を明らかにするものになります。
本邦の重症COVID-19患者さんにおいて、死亡や人工呼吸管理日数、気管切開の有無について検討することは、治療の質的向上に繋がる重要な事項と考えます。
研究の目的と方法
本研究の目的は、重症COVID-19患者さんの栄養予後指数と生存の有無や人工呼吸管理日数などの関連について検討することです。日常診療で得られた臨床データ(年齢、性別、身体所見や生化学検査など)を電子カルテから集計・統計分析を行う後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、令和3年7月1日~令和5年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センターに入院し人工呼吸管理を施行した患者さんを対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究終了後の収集したデータは、鍵をかけたファイルにて5年間保管ののち、破棄いたします。
調査期間
研究対象期間:令和3年 7月 1日~令和 5年 3月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 7年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 / 熊本大学大学院 医学教育部 医学専攻 外科系 臨床国際協力学講座
加來正之
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
電話:096-353-6501
187.院内救急コールの事例分析
研究の概要
院内救急コールシステムは、院内心停止や予期せぬ急変時に救命を第一優先として病院全体で対応するシステムです。近年は、急変時の迅速対応の重要性が認識され、院内迅速対応システム(rapid response system ; RRS)導入が病院機能評価の項目となっており、当院でも2022年より導入されました。RRS導入以前の院内緊急コールの事例分析を行い、院内救急コール対象者の特徴ならびに予後を明らかにすることで院内救急コールに関する教育やRRSのスムーズな導入に役立つものと考えます。
研究の目的と方法
今回の研究は、当院における院内救急コール対象者の特徴ならびに予後を明らかにすることを目的とします。本研究では、国立病院機構熊本医療センターに入院または外来受診された患者さんのうち、2009年3月31日~2022年3月31日までの院内コールが要請された方を対象としています。研究対象症例数は、約170名です。日常診療で得られたデータ(年齢、性別、身体所見、検査内容、検査値、最終診断、治療状況、転帰)を電子カルテから集計いたします。
本研究の参加について
これにより、患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。ご自身のデータを本研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせまでご連絡ください。
調査する内容
本研究は、新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究対象者(患者さん)の個人情報(氏名、住所、電話番号、カルテ番号など)は、記載せず、対応表を作成して管理しますので、個人情報は特定されません。
調査期間
調査対象期間:2009年3月31日~2022年3月31日
研究実施期間:倫理委員会承認後~2024年3月31日
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や学術論文で発表いたします。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 総合診療科 辻 隆宏
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 総合診療科 辻 隆宏
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 総合診療科 辻 隆宏 電話:096-353-6501
186.C型慢性肝疾患に対する直接作用型抗ウイルス薬(Direct Acting Antivirals: DAA)治療後の予後の観察研究
研究対象者
2017年3月3日より国立病院機構熊本医療センターにおいてC型慢性肝疾患に対する直接作用型抗ウイルス薬(Direct Acting Antivirals: DAA)治療を受けた患者様
研究協力のお願い
この研究は、国立病院機構熊本医療センターでC型慢性肝疾患に対する直接作用型抗ウイルス薬(Direct ActingAntivirals:DAA)治療を受けた患者様の予後に関する調査を、熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学を研究事務局として熊本県内の関連施設の多施設共同研究として行うことになりました。対象となる患者様は、熊本大学消化器内科ならびに関連施設でDAA治療を行いウイルス駆除が得られたC型慢性肝疾患の患者様です。この研究は、過去の診療記録を用いて行われますので、該当する方の現在・未来の診療内容には全く影響を与えませんし、不利益を受けることもありません。解析にあたっては、個人情報は匿名化させていただき、その保護は徹底致します。学会や論文などによる結果発表に際しては、患者様個人の特定が可能名情報は全て削除致します。
対象となる患者様で、本研究に関して不明な点がある場合、あるいはデータの利用に同意されない場合には、以下にご連絡いただきたいと思います。なお、本研究は熊本大学の「人を対象とする生命科学・医学系研究臨床研究部門倫理委員会」の承認を得ております。ま た、この研究への参加をお断りになった場合にも、将来にわたって当科における診療・治療において不利益を被ることはございませんので、ご安心下さい。
情報等の使用について、直接に説明して同意はいただかずに、このお知らせをもって研究に関する事項を公開いたします。対象となる方におかれましては、研究の主旨・方法をご理解いただきますようお願い申し上げます。
この研究への参加を希望されない場合、あるいは、研究に関するご質問は下記の問い合わせ先へご連絡ください。
研究の目的と方法
(研究の目的について)
本臨床研究では直接作用型抗ウイルス薬(Direct Acting Antivirals: DAA)を受けられたC型慢性肝疾患の患者様を対象としております。今後増加が予想されるDAAの治療を受けられた方のウイルス駆除率は高く、その治療を受けられた方のその後の癌の発生や生命予後などを調査することで、効率的な治療後の経過観察の方法などが期待されます。
(研究の方法について)
当院の電子カルテシステムから画像検査および検体検査(血液および尿検査)項目を抽出し、匿名化された状態でデータベースを構築し、各種解析を行います。研究期間は 2017年3月 3日~2025年12月31日です。
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター:電話番号096-353-6501 消化器内科 研究責任者 杉 和洋
185.仮想単色X線画像を用いた大腸癌術前3D-CTにおける静脈描出能の検討
研究の概要
大腸癌術前に目的臓器と動脈の位置関係を、非侵襲的な検査であるthree-dimensional computed tomography(3D-CT)画像によってある程度把握することは、迅速かつ安全な手術を行う上で有用である。さらに、動脈に加えて静脈を抽出することで、リンパ節郭清領域のシミュレーションとしても大きな役割を果たす。しかし、3D-CT撮影では、静脈優位相での撮影においても静脈CT値は低く、他臓器や血管との分離が困難であり、3D作成には多大な時間と労力を要する。
当院では、dual energy CT撮影が可能なCT装置を有し、2種類の異なる管電圧(X線エネルギー)を用いて撮影をする技術で、様々な画像解析を行うことができる。その中で、仮想単色X線画像(virtual monochromatic spectral image:VMI)はX線エネルギーを1keV毎にエネルギーを選択し画像再構成することが可能であるため、コントラストの向上やアーチファクト軽減、病変の検出能向上などが期待されている。X線エネルギーを低く設定し画像再構成したVMIの低keV画像は、造影剤のCT値を上昇させるために、造影剤を構成するヨードのk吸収端(33.2keV)に近づけるができる。しかし、VMIの低keV画像は画像ノイズが増加することが問題とされている。
本研究では、VMIの低keV画像を用いることで、静脈のCT値を上昇できないか、低keV画像のCT値や画像ノイズ特性をファントムや臨床画像を用いて調べ、静脈3D構築を目的とした静脈抽出における低keV画像の有用性について検討する。
研究の目的と方法
1. マルチエナジーCTファントムによるCT値評価
2. 水ファントムによるノイズ評価
3. 大腸癌術前3D-CT画像によるCT値評価
大腸癌術前に静脈3D構築依頼を受けた患者症例で、過去の造影CT画像を用いた後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な画像データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、令和4年4月1日~令和5年7月31日までの期間中、国立病院機構熊本医療センター放射線科にて大腸癌術前CT検査を実施された患者さんを対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存のCT画像のみを用いて実施する研究です。
調査期間
研究対象期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和5年10月31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構 熊本医療センター 放射線科 診療放射線技師 坂田 潤一
当院における研究責任者
国立病院機構 熊本医療センター 放射線科 診療放射線技師 坂田 潤一
問い合わせ先
国立病院機構 熊本医療センター 放射線科 診療放射線技師 坂田 潤一
電話番号:096-353-6501(代表)
184.院内発症の高血糖症患者の病態を解明するための後ろ向き観察研究
研究の概要
入院中の患者さんにおいて、高血糖症は患者さんの病態を悪化させるため、その予防が重要です。しかし、入院中の患者さんにおいては、様々な治療や入院中の患者さんの病態そのものが高血糖症を誘発することがあります。今回の研究では、入院中に発症した高血糖症の患者において、その誘因と考えられる因子を調査します。本研究により、高血糖症の発症要因がわかれば、入院中の患者さんにおける高血糖症の発症を予防することに繋がり、重要であると思われます。
研究の目的と方法
本研究では、2016年4月1日~2023年3月31日に国立病院機構熊本医療センターで入院治療を受けた患者さんを対象としています。日常診療で得られたデータを電子カルテから集計いたします。
本研究の参加について
本研究により患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究に扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、新たに試料・情報を取得することはなく、既存のカルテデータ((年齢、性別、検査値、治療状況、合併症・転帰など)を用いて実施する研究です。研究対象者(患者さん)の個人情報(氏名、住所、電話番号)は記載せず、個人情報は特定されません。
調査期間
研究期間:倫理審査許可日~2026年3月31日(調査対象期間:2016年4月1日~2023年3月31日)
研究成果の発表
研究成果については、学会、論文などでの発表を予定しています。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病内分泌内科 西川武志
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病内分泌内科 西川武志
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 糖尿病内分泌内科 西川武志 電話 096-353-6501
183.血液循環腫瘍DNA陰性の高リスクStage II及び低リスクStage III結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのCAPOX療法と手術単独を比較するランダム化第III相比較試験(VEGA trial)
研究の対象
2020年7月以降に血液循環腫瘍DNA陰性の高リスクStage II及び低リスクStage III結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としてのCAPOX療法と手術単独を比較するランダム化第III相比較試験(VEGA trial)に参加された方
研究の目的と方法
本研究では血液中のがん細胞由来DNA(ctDNA/circulating tumor DNA)が術後に陰性のStage IIまたはStage IIIの結腸がんの患者さんを対象として、従来の術後化学療法を行う群と、あらたな提案である経過観察群の比較を行い、再発率に差がないかを検証します。
公開原稿で対象としている患者さんからは、本研究で収集した臨床で得られるデータと患者さんから既に同意が得られているレジストリ研究(※)の中で行われたctDNA解析結果について統計解析を行います。
なお、本研究の研究期間は研究許可日~2031年3月31日までです。
※根治的外科治療可能の結腸・直腸癌を対象としたレジストリ研究:外科治療で根治可能の結腸・直腸がんの患者さんにおける臨床情報と、がん組織および血中にあるがん細胞由来の遺伝子の検査結果を集め、患者さん一人一人に合わせた手術後の治療介入や定期検査を提案するために必要なデータを作成する研究で、本研究に参加される前に説明をうけている研究です。(UMIN ID:UMIN000039205)
研究に用いる試料・情報の種類
すでに本研究でご提供いただいた臨床情報(画像・血液検査結果を含む臨床経過等)及びレジストリ研究で得られた遺伝子解析結果を利用します。患者さんからのご希望があれば、その方の臨床情報や遺伝子解析結果は研究に利用しないように配慮いたします。なお、本研究は登録番号と患者さんのカルテ番号等を併記する対応表を用いて行います。対応表は、本院の研究責任者が本院内で厳重に管理します。
外部への試料・情報の提供
この公開原稿で対象としている患者さんからの本研究で得られるデータとレジストリ研究から得られた遺伝子解析結果は、統計解析を実施する海外のMayo Clinic(米国)及びNatera社(米国)に送付され解析されます。研究に利用する患者さんのデータからは、解析を開始する前に、当院にて氏名などが削除され、代わりに新しくこの研究専用の登録番号がつけられることで匿名化した臨床情報等が提供されます。
(海外統計解析実施機関)
本研究に関する統計解析は、Mayo ClinicとNatera社及び国立がん研究センター東病院で実施します。
統計解析実施先名称:Mayo Clinic Cancer Center
住所:200 First Street SW, Rochester, MN 55905, United States of America
Mayo Clinicプライバシーポリシー:
(https://www.mayoclinic.org/about-this-site/privacy-policy)
統計解析実施先名称:Natera Inc.
住所:201 Industrial Road, Suite 410, San Carlos, CA, 94070, United States of America
Natera Inc. プライバシーポリシー:
(https://www.natera.com/privacy/)
外国における個人情報の保護に関する制度は以下から参照することができます。
研究の資金と利益相反
この公開原稿で対象としている患者さんからのデータにおける統計解析に関わる費用は、国立がん研究センター研究開発費、国立がん研究センター東病院消化管内科及び医薬品開発推進部門が有する研究費、日本医療研究開発機構からの研究費によりまかなわれます。この他に、共同研究契約に基づき株式会社アルファ‐Aから資金提供を受けて実施します。本研究における利益相反の管理は、参加施設それぞれが自施設の研究者に関して行っています。資金提供が研究結果に影響を及ぼすことがないように、研究の透明性、信頼性の確保を図りながら研究を実施します。
研究組織
研究代表者:札幌医科大学附属病院 消化器・総合、乳腺・内分泌外科 竹政 伊知朗
国立がん研究センター東病院 消化管内科 中村 能章
研究参加施設及び研究責任医師
本研究の参加施設と各施設の研究責任者は、下記ホームページでご確認いただけます。
問い合わせ先
本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。また、情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。
照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先 / 研究責任者:
研究責任者:外科 宮成 信友
連絡先:国立病院機構熊本医療センター 外科
連絡先:〒860-0008 熊本市中央区二の丸1-5
TEL : 096-353-6501(代)
182.成人の無菌性髄膜炎を適切に診断する上で有用な因子の探索
研究の概要
無菌性髄膜炎は、ウイルス感染が主な原因で、特異的な治療を要さずに軽快することが多いですが、時に脳炎、水頭症といった重篤な合併症を併発することがあります。診断する際に重要な徴候や所見として、頭痛、吐き気、項部硬直、Jolt accentuation、ケルニッヒ徴候、ブルジンスキー徴候などがありますが、いずれも非特異的なもので診断確定には髄液検査が必要です。その髄液検査も、合併症のリスクがある侵襲的な検査なので、検査を躊躇することで診断が遅れる可能性があります。そのため、無菌性髄膜炎の可能性を予測した上で、髄液検査を行うことが適切な診断を行う上で大切です。しかし、無菌性髄膜炎の適切な診断に焦点をあてた研究は多くありません。
今研究の結果から、無菌性髄膜炎の診断に関する要因や診断が遅れる要因を抽出することができれば、今後の臨床現場で、無菌性髄膜炎の適切な早期診断に繋がる可能性があります。
研究の目的と方法
今回の研究の目的は、当院に入院した成人の無菌性髄膜炎の患者を対象に診断が遅れた要因を検討し、適切な診断に有用な因子を探索することです。
本研究では、2013年1月~2022年12月に国立病院機構熊本医療センターで無賄性髄膜炎と診断された方を対象としています。患者背景(年齢、性別、慢性頭痛の有無、精神疾患の有無、解熱鎮痛薬の使用の有無、免疫抑制状態の有無、先行抗菌薬治療の有無、先行感染の有無)、状況要因(発症から受診までの期間、初診の病院、初診の診療科、初診の時間帯、発症季節)、疾患要因(最高体温、頭痛の有無、倦怠感の有無、嘔気嘔吐の有無、羞明の有無、関節痛の有無、発疹の有無、項部硬直の有無、Jolt accentuation陽性の有無、ケルニッヒ徴候の有無、ブルジンスキー徴候の有無)、初診から髄液検査までの時間、血液検査データなどを電子カルテから集計します。
本研究の参加について
これにより、患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。
ご自身のデータを本研究に使わないでほしいと希望される方、その他、研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先にご連絡ください。
調査する内容
本研究は、新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究対象者(患者さん)の個人情報(氏名、住所、電話番号、カルテ番号など)は記載せず、対応表を作成して管理しますので、個人情報は特定されません。
調査期間
研究対象期間:2013年1月1日~2022年12月31日まで
研究実施期間:2023年4月1日~2027年3月31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や学術論文で発表いたします。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 総合診療科 國友耕太郎
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 総合診療科 國友耕太郎
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター総合診療科 國友耕太郎 電話:096-353-6501
181.眼科手術における静脈麻酔による鎮静薬の有効性の評価
研究の概要
眼科手術を行う際の鎮静薬の有効性を評価するために診療情報を活用します。
研究の目的と方法
眼科手術を行う際に場合によっては静脈麻酔(点滴)で鎮静薬(睡眠薬)を投与する場合がありますが、その具体的な使用法や合併症への対応、有効性についてまとまった報告がありません。そこで、当院で治療を受けた患者様の診療情報(カルテなどの記録内容)を参考にデータを収集し解析し、鎮静薬の有効性を評価するとともに今後の眼科手術における鎮静薬のより良い使用方法について検討を行います。また、この研究のために患者様に対して新たに検査や診察を行うことはありません。
本研究の参加について
2019年4月1日から2021年3月31日までに当院眼科で手術を受けた患者様の内、手術時に静脈麻酔での鎮静薬を使用した患者様を対象とします。下記の調査内容をまとめたデータは特定の関係者以外がアクセスできない状態で行います。なお、この研究へご協力いただけない場合は、調査期間内であればいつでも拒否が可能であり、拒否された場合もその後の診療に不利益は一切ございません。調査期間終了後は個人情報とデータの照合ができなくなるため、調査期間終了後の参加拒否には対応できませんので予めご了承ください。研究参加拒否をご希望される場合やその他ご不明な点がございましたら下記問い合わせ先までご連絡ください。また、研究で得られたデータはセキュリティのあるUSBメモリに保存され、研究終了10年後に担当者がUSBメモリを裁断機等で物理的に破壊し、再現不能な形にした状態で破棄します。
調査する内容
年齢、性別、手術時の年齢、手術内容、鎮静薬を使用した理由、使用した鎮静薬の種類、鎮静に際して発生した合併症の有無とその種類、及びその対処法
調査期間
研究対象期間:平成31年4月1日~令和3年3月31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和6年12月31日まで
研究成果の発表
研究の結果は学会発表や学術雑誌等で公表します。
研究代表者
榮木 大輔(国立病院機構 熊本医療センター 眼科)
当院における研究責任者
榮木 大輔(国立病院機構 熊本医療センター 眼科)
問い合わせ先
1. 研究代表者
所属:国立病院機構 熊本医療センター 眼科 職名:医師 氏名:榮木 大輔
TEL:(代)096-353-6501 FAX:096-325-2519
〒860-0008 熊本県熊本市中央区二の丸1番5号 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター
2. 研究責任者
所属:国立病院機構 熊本医療センター 眼科 職名:医師 氏名:榮木 大輔
TEL:(代)096-353-6501 FAX:096-325-2519
〒860-0008 熊本県熊本市中央区二の丸1番5号 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター
180.A病院における日中及び夜間に搬送された重篤患者への早期医療介入の有効性の検証
研究の概要
当院に搬送された重篤患者さんの生命予後(生存退院率、社会復帰率)を明らかにし、当院における早期医療介入(病院前救急診療)の有効性を検証するために、診療情報を活用します。
研究の目的と方法
当院に救急搬送された重篤患者さんの診療情データ(調査する内容を参照)を収集し、患者さんの転帰について分析を行います。研究から得られたデータを元に、早期医療介入の有効性について検証を行います。また、この研究のためだけに新たに検査等を追加したりすることはありません。
本研究の参加について
2021年1月1日から2021年12月31日の間に、当院に救急搬送された重篤患者さんを対象とします。本研究においては、当院でデータ収集が行われた後に、共同研究機関である東京医療保健大学でデータの分析が行われます。収集されたデータには特定の関係者以外がアクセスできない状態で行います。なお、この研究へご協力いただけない場合は、調査期間内であれば、いつでも拒否が可能であり、一切診療上の不利益を受けることはございません。調査期間終了後は、個人情報とデータの照合が出来なくなりますので、調査期間終了後の参加拒否には対応できませんので予めご了承ください。研究参加拒否をご希望される場合やその他ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。なお、研究で得たデータはセキュリティのあるUSBメモリに保存され、研究終了10年後に指導教員がUSBを裁断機等で物理的に破壊し、再現不要な形にした状態で破棄いたします。
調査する内容
年齢、性別、入院日数、退院時の転帰、治療内容、救急隊の活動記録など
調査期間
調査対象期間:2021年1月1日から2021年12月31日
研究期間:倫理委員会の研究許可日~2024年3月29日
調査期間:倫理委員会の研究許可日~2023年4月30日
研究成果の発表
研究の成果は、学会発表や学術雑誌等で公表します。
問い合わせ先
1、研究責任者
所属:国立病院機構熊本医療センター看護部 職名:副看護師長 氏名:冨永 啓史
メールアドレス:kg022015@thcu.ac.jp
2、共同研究者
(1)所属:東京医療保健大学高度実践看護コース 1年 氏名:冨永 啓史(KG022015)
メールアドレス:kg022015@thcu.ac.jp
〒152- 8558 東京都目黒区東が丘2-5-1東京医療保健大学国立病院機構キャンパス
(2)所属:東京医療保健大学東が丘看護学部 職名:准教授 氏名:新山 真奈美(指導教員)
メールアドレス:m-niiyama@thcu.ac.jp 電話番号:03-5779-5032 (内線:202)
〒152- 8558 東京都目黒区東が丘2-5-1東京医療保健大学国立病院機構キャンパス
179.レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査
J-ASPECT study
研究の概要
本研究班は発足以降、厚生労働科学研究費補助金の循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業、および日本医療研究開発機構研究費の循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業として研究を続けています。
2013年度に実施した「日本脳神経外科医療の可視化に関する研究」においては「第34回日本脳神経外科コングレス総会」にて特別企画「医療におけるビッグデータの活用」と題して結果報告を行いました。
本研究班の基幹事業である「レセプト等情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査」では、過去9年間に本邦最大のデータベース(延べ755施設、DPCデータ約429万件、うち脳卒中症例約109万件)を構築しています。
研究の目的と方法
J-APECT study 参加施設から提供されるDPCデータ若しくは匿名化処理した医科レセプトデータにより、脳卒中、脳神経外科関連の傷病名等に基づいて症例を絞り込んだ全国規模の大規模データベースを構築し、今後の脳卒中関連の研究等に活用すると共に、医療施設の負荷を抑えた方法で脳卒中、脳神経外科医療に関する症例データベース構築を継続していくことを目的とします。
本研究の参加について
DPCデータ及びレセプトデータによる観察研究のため、身体的な利益及び不利益は生じることはありません。個人情報については、連続可能匿名化(試料・情報と研究対象者個人を連結する登録番号を設定し対応表を作成する。)対応表の管理方法はパスワードを設定したファイルとして管理し、外部と接続できないパソコンで厳重に取り扱います。参加施設のIDとの紐付けは行わないため、個人情報が特定されることはありません。
調査する内容
生年月日、性別、発症年月日、入院年月日、退院年月日、退院先
自宅郵便番号、診療報酬算定情報(DPC)
入院経路:救急車による搬送、他院よりの紹介
入院前および入院後生活自立度(modified Rankin Scale score,mRS)、入院中死亡の有無
初期重症度(JCS、GCS、NIHSS、Hunt&Hess grade、ICH grade、Hunt&Kosnik grade)
検査データ(腎機能、LDL-Chol、PT-INR)
搬送から画像撮影までの時間
搬送から組織プラスミノーゲン活性化因子(rtPA.,血栓溶解療法)投与までの時間
搬送から血管内治療のための穿刺までの時間
血栓回収を行った場合の再開通度(TICI grade)
rt-PA 静注療法または血管内再開通療法を施行した患者での36時間以内の症候性頭蓋内出血(NIHSS 4点以上悪化)の有無
退院90日後 modified Rankin Scale(mRS)
画像診断、検査の有無〔MRI、MRA、CT、脳血管造影、頚動脈超音波検査、撮影・検査未実施〕
リハビリテーションの有無、脳卒中・脳神経外科関連の診療にかかわる治療内容
*外部機関への研究データの提供
上記診療情報を、下記研究機関と共有して、共同で研究を進めます。
業務委託:健康保険医療情報総合研修所(PRRISM) 代表取締役社長 山口治紀
*外部機関からの情報の提供
当院は、J-ASPECT研究参加施設機関より学術研究目的で情報提供を受けます。
上記の「調査する内容」に示した内容の情報の提供を受けます。
調査期間
研究対象期間:2020年4月1日~2025年3月31日
研究実施期間:倫理委員会承認後~2026年3月31日まで
研究成果の発表
論文発表を行います。これまでJ-ASPECT studyから発表された英文原著論文は16編になります。
研究代表者
国立循環器病研究センター 病院長 飯原弘二
当院における研究責任者
国立病院機構 熊本医療センター 脳神経外科 中川隆志
問い合わせ先
国立循環器病研究センター 担当医師 西村邦宏 電話 06-6170-1070(代表)
国立病院機構 熊本医療センター 担当医師 中川隆志 電話 096-353-6501(代表)
本研究の研究内容、参加施設、患者さん向けの資料などにつきましては、研究班ホームページ
(J-ASPECT study)にて随時公開しております。
178.血液疾患患者を対象とした転倒転落リスク因子
研究の概要
過去に転倒転落のあった患者のカルテを遡り分析する事で、血液疾患患者独自の転倒転落因子を明らかにし、転倒予防対策の一助とするための研究です。
研究の目的と方法
過去に転倒転落のあった血液疾患患者の記録を遡る事で血液疾患患者独自の転倒転落因子を明らかにし、転倒転落防止対策に対する示唆を得るための研究です。
熊本医療センター6南病棟で令和3年4月~令和4年9月の間に転倒転落のあった患者の電子カルテを後方的に調査し、転倒転落した際の発熱の有無や血液データ、化学療法何日目かなどの情報と看護師がアセスメントした内容の看護記録をカテゴリー化し、相互関係を分析します。
本研究の参加について
これにより患者さんへ新たな検査や費用負担となることはありません。また、研究で扱う情報は個人が特定されないよう配慮いたします。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力お願いします。収集したデータは研究終了後、速やかに破棄いたします。万一、本研究にご自身のデータを使用しないでほしいと希望される方は下記の問い合わせ先までご連絡いただきますと集計から外させていただき、調査を中止させていただくことが可能です。ただし、学会発表後や論文報告後は集計から外すことは現実的に不可能となります。
調査する内容
過去に転倒転落のあった血液疾患患者の記録(年齢、性別、転倒時の発熱の有無、検査データ:白血球、CRP、血小板値、転倒転落アセスメントツールの点数・リスク評価、化学療法何日目か、転倒に対する意識など)と看護師のアセスメントした内容の看護記録の相互関係を分析する事で、血液疾患患者独自の転倒転落因子の現状を調査します。本研究は新たな試料・情報を取得する事なく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。
調査期間
研究対象期間:令和3年4月1日~令和4年9月30日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和5年3月31日まで
研究成果の発表
結果を学会で発表したり、論文に投稿させていただきます。
研究代表者
熊本医療センター6南病棟 副看護師長 藤島 由香利
当院における研究責任者
熊本医療センター6南病棟 副看護師長 藤島 由香利
問い合わせ先
860-0008
熊本県熊本市中央区二の丸1-5
国立病院機構熊本医療センター 6南病棟 副看護師長 藤島 由香利
電話:096-353-6501(代表)
177.肝細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害薬と血管新生阻害薬併用療法(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)の治療効果および有害事象に関する研究
研究対象者
2020年12月より国立病院機構熊本医療センターにおいてテセントリク+アバスチン(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)治療を受けた患者様
研究協力のお願い
この研究は、国立病院機構熊本医療センターでテセントリク+アバスチン(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)治療を受けた患者様の治療効果と有害事象(副作用)を解析することにより、患者様に病状に応じた最適な医療を提供することを目指すためのものです。
情報等の使用について、直接に説明して同意はいただかずに、このお知らせをもって研究に関する事項を公開いたします。対象となる方におかれましては、研究の主旨・方法をご理解いただきますようお願い申し上げます。
この研究への参加を希望されない場合、あるいは、研究に関するご質問は下記の問い合わせ先へご連絡ください。
研究の目的と方法
(研究の目的について)
2020年9月より切除不能肝細胞癌の一次治療として保険診療可能となった免疫チェックポイント阻害薬と血管新生阻害薬併用療法(アテゾリズマブ+ベバシズマブ)はこれまでのソラフェニブやレンバチニブをはじめとする分子標的薬に比べ生存期間の延長や腫瘍の縮小効果において高い治療効果を示しています。一方、副作用として、これまでの分子標的薬にない免疫原性有害事象(irAE)の発現が起こることも判っています(IMbrave150試験)。当院では2020年12月より切除不能肝細胞癌に対して本治療を行っていますが、自施設での症例に対して臨床的解析を行い、治療効果と有害事象を明らかにすることを目的とします。
(研究の方法について)
当院の電子カルテシステムから画像検査および検体検査(血液および尿検査)項目を抽出し、匿名化された状態でデータベースを構築し、各種解析を行います。研究期間は 2020年12月1日~2023年11月30日です。
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター:電話番号096-353-6501 消化器内科
研究責任者 杉 和洋
176.性索間質性精巣腫瘍の長期予後・病理標本アーカイブズの構築に関する 多機関後ろ向き共同研究
過去に通院又は入院された患者さままたはご家族の方へ(臨床研究に関する情報)
当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、患者さまの診療情報および研究用に保管された検体を用いて行います。このような研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)」の規定により、研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、以下の連絡先へご照会ください。
研究の目的
希少疾患であるセルトリ細胞腫、ライディッヒ細胞腫、顆粒膜細胞腫を代表とする性索間質性精巣腫瘍の患者さんの手術検体および診療情報をご提供いただき、性索間質性精巣腫瘍の病理学的特徴、臨床的特徴、治療成績や予後を集積し今後の診断精度の向上に役立てることを目的としています。
研究の方法
希少疾患であるセルトリ細胞腫、ライディッヒ細胞腫、顆粒膜細胞腫を代表とする性索間質性精巣腫瘍の患者さんの手術検体および診療情報をご提供いただき、性索間質性精巣腫瘍の病理学的特徴、臨床的特徴、治療成績や予後を集積し今後の診断精度の向上に役立てることを目的としています。
本研究の参加について
・対象となる患者さま
性索間質性精巣腫瘍の患者さんで、各機関の調査可能開始年から2021年12月の間に精巣摘除術・精巣部分切除術・腫瘍核出術を受けた方
・利用する検体・情報
検体:手術を行った際の組織検体
情報:
① 対象者基本情報:年齢、性別、診断名、既往歴、発見の契機、随伴症状、採血結果(腫瘍マーカー、性ホルモン値等)、治療経過、手術日、手術の内容、化学療法実施の有無、実施症例に関しては化学療法の内容、放射線療法の実施の有無、実施症例に関しては放射線治療の内容
② 画像検査所見(CT画像、MRI画像)
③ 病理結果(前述の如くWEBベースでの利用を想定した病理アーカイブズの作成も行う)
④ 経過中の採血結果(腫瘍マーカー、性ホルモン値等)
⑤ 再発の有無、再発部位、再発時期、再発時の治療内容
⑥ 最終転帰
・送付方法
この研究は、上記の研究機関で実施します。上記の検体は、中央病理解析のため、病理研究事務局である愛知医科大学病院病理診断科(責任者:都築豊徳)、防衛医科大学校病院検査部(責任者:宮居弘輔)に送付します。上記のカルテ情報は、研究事務局である北海道大学大学院医学研究院 腎泌尿器外科学教室(責任者:安部崇重)に電子的配信で送付します。
調査期間
実施許可日~2025年3月31日
この研究について、研究計画や関係する資料、ご自身に関する情報をお知りになりたい場合は、他の患者さんの個人情報や研究全体に支障となる事項以外はお知らせすることができます。
研究に利用する患者さんの情報に関しては、お名前、住所など、患者さん個人を特定できる情報は削除して管理いたします。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる情報は削除して利用いたします。
*上記の研究に情報・検体を利用することをご了解いただけない場合は以下にご連絡ください。
研究代表機関名・研究代表者名・所属
No | 共同研究機関 | 研究責任者 | 機関長名 |
| 1 | 北海道大学医学研究科腎泌尿器外科 | 安部 崇重 | 渥美 達也 |
| 2 | 神奈川県立がんセンター | 岸田 健 | 古瀬 純司 |
| 3 | 市立秋田総合病院 | 石田 俊哉 | 伊藤 誠司 |
| 4 | 国際医療福祉大学病院 | 内田 克紀 | 鈴木 裕 |
| 5 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 | 日比 初紀 | 飯田 邦夫 |
| 6 | 社会保険 田川病院 | 矢野 雄太 | 黒松 肇 |
| 7 | 石川県立中央病院 | 浦田 聡子 | 岡田 俊英 |
| 8 | 国立病院機構熊本医療センター | 菊川 浩明 | 高橋 毅 |
| 9 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 湯村 寧 | 榊原 秀也 |
| 10 | 群馬県立がんセンター | 蓮見 勝 | 鹿沼 達哉 |
| 11 | 平塚共済病院 | 宇田川 幸一 | 稲瀬 直彦 |
| 12 | 社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院 | 西松 寛明 | 平野 美和 |
| 13 | 岩手医科大学附属病院 | 小原 航 | 小笠原 邦昭 |
| 14 | 愛媛大学医学部附属病院 | 菊川 忠彦 | 杉山 隆 |
| 15 | 岐阜市民病院 | 米田 尚生 | 冨田 栄一 |
| 16 | 九州大学 (形態機能病理学) | 孝橋 賢一 | 中村 雅史 |
| 17 | がんセンター新潟病院 | 小林 和博 | 佐藤 信昭 |
| 18 | 藤田医科大学 | 高原 健 | 白木 良一 |
| 19 | JCHO中京病院 | 辻 克和 | 後藤 百万 |
| 20 | 労働者健康安全機構 関東労災病院 | 武内 巧 | 根本 繁 |
| 21 | 市立札幌病院 | 三浪 圭太 | 西川 秀司 |
| 22 | 三重大学医学部附属病院 | 井上 貴博 | 池田 智明 |
| 23 | 国立病院機構 仙台医療センター | 齋藤 英郎 | 上之原 広司 |
| 24 | 宮崎県立宮崎病院 | 黒岩 顕太郎 | 嶋本 富博 |
| 25 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 斎藤 一隆 | 奥田 泰久 |
| 26 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 吉田 哲也 | 田中 俊宏 |
| 27 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 海野 智之 | 大石 強 |
| 28 | 兵庫県立西宮病院 | 岸川 英史 | 野口 眞三郎 |
| 29 | 大分大学医学部 | 秦 聡孝 | 杉尾 賢二 |
| 30 | 京都市立病院 | 清川 岳彦 | 黒田 啓史 |
| 31 | 大阪済生会 野江病院 | 河 源 | 福田 和彦 |
| 32 | 長野市民病院 | 加藤 晴朗 | 池田 宇一 |
| 33 | 県立尼崎総合医療センター | 山田 裕二 | 平家 俊男 |
| 34 | 埼玉県立がんセンター | 影山 幸雄 | 影山 幸雄 |
| 35 | 防衛医科大学校 | 伊藤 敬一 | 塩谷彰浩 |
| 36 | 帝京大学医学部 | 金子 智之 | 川村 雅文 |
| 37 | 東京大学医学部附属病院 | 田口 慧 | 瀬戸 泰之 |
| 38 | 兵庫医科大学病院 | 山本 新吾 | 阪上 雅史 |
| 39 | 宮崎大学 | 向井 尚一郎 | 帖佐 悦男 |
| 40 | 山梨大学医学部附属病院 | 三井 貴彦 | 榎本 信幸 |
| 41 | 弘前大学医学部附属病院 | 畠山 真吾 | 大山 力 |
| 42 | 名古屋市立大学病院 | 内木 拓 | 間瀬 光人 |
| 43 | 北海道済生会小樽病院 | 堀田 浩貴 | 和田 卓郎 |
| 44 | 札幌医科大学附属病院 | 前鼻 健志 | 土橋 和文 |
| 45 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 小林 一樹 | 長堀 薫 |
| 46 | 公益財団法人がん研究会有明病院 | 湯浅 健 | 佐野 武 |
| 47 | 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 古林 伸紀 | 藤也 寸志 |
| 48 | 筑波大学附属病院 | 河原 貴史 | 原 晃 |
| 49 | 関西医科大学附属病院 | 齊藤 亮一 | 松田 公志 |
| 50 | 岩手県立胆沢病院 | 米田 真也 | 勝又 宇一郎 |
| 51 | 徳島大学病院 | 大豆本 圭 | 香美 祥二 |
| 52 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 木村 高弘 | 小島 博己 |
| 53 | 山口大学医学部附属病院 | 松本 洋明 | 杉野 法広 |
| 54 | 網走厚生病院 | 望月 端吾 | 中野 詩郎 |
| 55 | JCHO仙台病院 | 泉 秀明 | 村上 栄一 |
| 56 | 友愛記念病院 | 阿部 英行 | 加藤 奨一 |
| 57 | 岩見沢市立総合病院 | 片野 英典 | 小倉 滋明 |
| 58 | 九州大学病院(泌尿器科) | 柏木 英志 | 中村 雅史 |
| 59 | 国立がん研究センター中央病院 | 松井 喜之 | 島田 和明 |
| 60 | 京都大学医学部附属病院 | 小林 恭 | 宮本 享 |
| 61 | 国立大学法人 浜松医科大学 | 三宅 秀明 | 今野 弘之 |
| 62 | 秋田大学医学部附属病院 | 成田 伸太郎 | 南谷 佳弘 |
| 63 | 大阪公立大学 | 加藤 実 | 中村 博亮 |
| 64 | 愛知医科大学病院 | 佐々 直人 | 道勇 学 |
| 65 | 気仙沼市立病院 | 竹本 淳 | 横田 憲一 |
| 66 | 手稲渓仁会病院 | 柏木 明 | 古田 康 |
| 67 | 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 橋根 勝義 | 山下 素弘 |
| 68 | 八戸市立市民病院 | 佐藤 真彦 | 三浦 一章 |
| 69 | 北海道がんセンター | 原林 透 | 加藤 秀則 |
| 70 | 国立病院機構 水戸医療センター | 飯沼 昌宏 | 米野 琢哉 |
| 71 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 北村 寛 | 林 篤志 |
| 72 | 東北大学病院 | 山下 慎一 | 冨永 悌二 |
| 73 | 長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 鈴木 尚徳 | 宮下 俊彦 |
| 74 | 宮城県立こども病院 | 坂井 清英 | 今泉 益栄 |
| 75 | 刈谷豊田総合病院 | 成田 知弥 | 田中 守嗣 |
| 76 | 結城病院 | 瑞木 亨 | 大木 準 |
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 泌尿器科 菊川浩明
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター泌尿器科
担当医師:_山中達郎
住所:熊本市中央区二の丸1-5
電話:096-353-6501 FAX:096-353-6563
175.がん薬物療法チームにおける管理栄養士の介入効果に関する研究
研究の概要
がん患者の治療支援として管理栄養士の介入は一定の効果を得てきました。加えて、NSTなど栄養サポートに特化したチーム医療においても効果を示すことができている。さらに、「がん病態栄養専門管理栄養士」なる管理栄養士の認定資格が診療報酬としても認められています。しかし、チームにおける「がん病態栄養専門管理栄養士」の効果についての報告は見られていません。今回、がん拠点病院において、抗がん剤治療の支援を目的としたがん薬物療法チームにおける「がん病態栄養専門管理栄養士」の効果を示すことを目的にしました。つまり、栄養介入の目的、管理栄養士介入がエネルギーたんぱく質摂取量に及ぼす影響、身体所見や血液データに及ぼす影響を検証することとしました。
研究の目的と方法
本研究の目的は、がん薬物療法チームにおける管理栄養士の介入効果について検討することです。日常診療で得られた臨床データ(年齢、性別、身体所見や生化学検査など)を電子カルテから集計・統計分析を行う後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください
調査する内容
本研究は、令和3年4月1日~令和4年3月31日の期間中、国立病院機構熊本医療センターがん薬物療法チームが介入し、栄養食事指導を実施した患者さんを対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究終了後の収集したデータは、鍵をかけたファイルにて5年間保管ののち、破棄いたします。
調査期間
研究対象期間:令和3年 4月 1日~令和 4年 3月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 6年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
電話:096-353-6501
174.身体合併症を伴う精神科病棟での身体拘束の実態と身体拘束最小化への課題
研究の概要
精神科身体合併症病棟で身体拘束を実施した患者を対象に、疾患や診療科別に分析し身体拘束の実態を明らかにすることで、身体拘束最小化へ取り組むための研究です。
研究の目的と方法
身体合併症を伴う精神科病棟での身体拘束の実態を明らかにすることで、身体拘最小化へ向けた課題を明らかにするための研究です。熊本医療センター精神科病棟に入院し、治療上身体拘束が必要となった患者さまを対象にその理由や経過をカルテや台帳よりデータを収集し調査します。
本研究の参加について
該当する患者さまの電子カルテの情報を、当方で集計させていただきますので、改めてアンケートに答えていただいたり、同意書をいただいたりすることはございません。ご参加の意思を改めて確認することもございません。個人情報はすべて匿名化して報告させていただきますので、個人のプライバジーは守られています。収集したデータは研究終了後、速やかに破棄いたします。万一、この調査に参加したくないという患者様がいらっしゃいましたら、末尾の問い合わせ先にご連絡いただきますと集計から外させていただき、調査を中止させていただくことが可能です。ただし、学会発表後や論文報告後は集計から外すことは現実的に不可能になります。
調査する内容
性別、年齢、精神科診断、身体合併症診断、身体拘束理由、診療科、手術の有無、使用した薬剤、入院日数、などです。
調査期間
研究対象期間:令和 3年 9月 1日~令和 3年 11月 30日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 5年 3月 31日まで
研究成果の発表
結果を学会で発表したり、論文に投稿させていただきます。
研究代表者
7南病棟 看護師 荒川 唯
当院における研究責任者
7南病棟 看護師 荒川 唯
問い合わせ先
860-0008
熊本市中央区二の丸1-5
国立病院機構熊本医療センター 7南病棟 看護師 荒川 唯
電話 096-353-6501(代表)
173.HER2陽性切除不能進行・再発胃癌に対するトラスツズマブデルクステカンの有効性・安全性を評価する後ろ向きコホート研究(EN-DEAVOR研究)
研究の目的と方法
この研究は、エンハーツ®による治療が実施された胃がん患者さんを対象に、この薬剤の治療結果を確認し、同じような病気を持つ患者さんに、より適切な治療法を示すことを目的としています。
研究実施期間は、実施承認日もしくは2022年10月1日のいずれか遅い日から2024年3月31日までです。
本研究は第一三共株式会社から研究資金を受領して行います。
本研究の参加について
2020年9月25日から2021年9月30日までに、国立病院機構熊本医療センターにて胃がんの治療としてトラスツズマブデルクステカン(製品名:エンハーツ®)を初めて投薬された方
研究に用いる試料・情報の種類
この研究では、患者さんの2022年9月30日までの通常診療で得られた情報(生年月、性別、治療薬の投薬状況、疾患の経過、有害事象の発現の状況等)を診療録に記録されている内容から調べます。
外部への試料・情報の提供
この研究は外部の研究機関と共同で行いますので、患者さん個人のデータを外部の研究機関と共有します。しかしながら、患者さんから提供された研究に関するデータは、個人が特定される情報は削除して、研究用番号をつけて個人を識別します。個人と研究用番号を照合する情報は、当病院の研究責任者が保管・管理しますので外部の研究機関が患者さん個人を特定することはできません。
研究組織
名古屋大学医学部附属病院 小寺 泰弘
愛知県がんセンター 室 圭
千葉県がんセンター 三梨 桂子
国立がん研究センター中央病院 岩佐 悟
埼玉県立がんセンター 原 浩樹
九州がんセンター 江崎 泰斗
近畿大学病院 川上 尚人
神奈川県立がんセンター 町田 望
北海道がんセンター 佐川 保
JA広島総合病院 杉山 陽一
埼玉医科大学国際医療センター 三原 良明
静岡がんセンター 川上 武志
大阪国際がんセンター 杉本 直俊
大阪市立総合医療センター 秋吉 宏平
横浜市立大学附属市民総合医療センター 國崎 主税
広島市立北部医療センター安佐市民病院 檜原 淳
広島市立広島市民病院 丁田 泰宏
県立広島病院 篠崎 勝則
秋田大学医学部附属病院 柴田 浩行
日本海総合病院 橋爪 英二
富山大学附属病院 安田 一朗
筑波大学附属病院 山本 祥之
呉医療センター 田代 裕尊
さいたま市立病院 関根 克敏
群馬県立がんセンター 保坂 尚志
慶應義塾大学病院 浜本 康夫
秋田赤十字病院 武藤 理
土浦協同病院 草野 史彦
福岡大学病院 長谷川 傑
トヨタ記念病院 大田 亜希子
京都大学医学部附属病院 松原 淳一
山形大学医学部附属病院 鈴木 修平
小牧市民病院 小林 大介
聖マリアンナ医科大学 新井 裕之
釧路労災病院 澤田 憲太郎
熊本医療センター 境 健爾
大崎市民病院 坂本 康寛
市立豊中病院 川瀬 朋乃
東京都済生会中央病院 船越 信介
第一三共株式会社 藤原 康策
問い合わせ先
本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。
また、情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。
照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先
研究事務局:国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科 榮 達智
住所:〒860·0008熊本県熊本市中央区二の丸1-5
TEL 096·353·6501 FAX 096·325·2519
研究責任者
国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科 境 健爾
研究代表者
名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学 小寺 泰弘
愛知県がんセンター薬物療法部 室 圭
172.新型コロナウイルス感染症(SARS-COV-2:COVID-19)重症患者における栄養評価に関する研究
研究の概要
COVID-19重症患者に対する治療において、栄養サポートを組み合わせることが重要とされています。集中治療室(Intensive Care Unit:ICU)入室の重症患者の栄養療法開始については栄養評価や重症度などのリスク判定を行うことが提言されています。しかし、日本におけるCOVID-19重症患者に対する簡便な栄養評価に関する報告は少ないのが現状です。本研究は治療中に採血項目として実施されているアルブミンと総リンパ球数を用いた計算式PNIが人工呼吸管理日数・ICU在室日数と関連があるかを調査するものになります。
現状、本邦においてCOVID-19重症患者の栄養評価についての報告は少なく、人工呼吸管理日数・ICU在室日数への影響を検証することは、治療の一助となる重要な事項と考えます。
研究の目的と方法
本研究の目的は、COVID-19重症患者の栄養状態と人工呼吸管理日数・ICU在室日数について検討することです。日常診療で得られた臨床データ(年齢、性別、身体所見や生化学検査など)を電子カルテから集計・統計分析を行う後ろ向き研究です。
本研究の参加について
これにより患者さんに新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究で扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
本研究は、令和2年4月1日~令和4年9月30日の期間中、国立病院機構熊本医療センターICUに入室した患者さんを対象としています。新たに試料・情報を取得することはなく、既存カルテ情報のみを用いて実施する研究です。研究終了後の収集したデータは、鍵をかけたファイルにて5年間保管ののち、破棄いたします。
調査期間
研究対象期間:令和2年 4月 1日~令和 4年 9月 30日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和 6年 3月 31日まで
研究成果の発表
調査した患者さんのデータは、集団として分析し、学会や論文で発表します。また、個々の患者さんのデータを発表するときも、個人が特定されることはありません。
研究代表者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 栄養管理室 加來正之
電話:096-353-6501
171.本邦心大血管リハビリテーションの問題点の抽出と対策の検討
研究の概要
2014年1月1日~2014年12月31日に入院した、主傷病名、入院契機病名、医療資源最大病名、医療資源2番目に投入した病名で急性心筋梗塞の病名が含まれた20歳以上の患者さまを対象とし、通常診療下で得られた診療情報を収集する研究です。
研究の目的と方法
目的:心臓リハビリテーションの量や質による急性心筋梗塞患者の予後改善効果を確認するとともに、保険診療における妥当性などに関する問題点を抽出し、それらを検証することを目的としています。
方法:本研究はカルテ等情報を用いて実施します。通常の診療下で得られる情報を使用するため、本研究のために新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、収集された情報は、匿名化の対応を行い、匿名化された情報のみをデータベースに登録を行います。
本研究の参加について
本研究の参加・不参加に関わらず利益・不利益が生じることはありません。情報が当該研究に用いられることについて、患者さま又は患者さまのご家族よりお申し出があった場合、研究の対象といたしませんので、下記の「お問合せ先」までお申し出ください。
調査する内容
電子カルテなどに記載のある以下の診療情報を利用します。
心血管疾患、併存症・合併症、入院までの治療歴、過去の心臓リハビリテーション施行歴
【入院中】
身体所見、、心臓リハビリテーション、臨床検査データ、予後
【予後調査】
退院後の心臓リハビリテーション継続の有無、身体所見および臨床検査データ、予後など
調査期間
研究対象期間:2014年1月1日~2014年12月31日
研究実施期間:倫理委員会承認後~2024年9月30日まで
研究成果の発表
本研究で得られた結果は、学会や医学雑誌等で発表される予定ですが、このような場合においでも、患者さまを特定できるような個人情報などのプライバシーに関するものが公表されることは一切ありません。
研究代表者
研究代表者:福岡大学医学部 心臓・血管内科学講座 教授 三浦伸一郎
当院における研究責任者
国立病院機構熊本医療センター 循環器内科 藤本和輝
問い合わせ先
本研究にご自身のデータを使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際には、以下の連絡先までお問合せください。
国立病院機構熊本医療センター 循環器内科 藤本和輝
電話:096-353-6501(代表)
170.生物学的マーカーは、エンド・オプ・ライフ ケアに関する話し合いの時期を考えるための客観的指標になりうる
研究の概要
生物学的マーカーが人生終末期のケア(エンド・オブ・ライフケア)の話し合いの時期を決定する指標になりうるかを検討した。2017年1月から3年間に熊本医療センター腫瘍内科にて入院診療を行ったがんの終末期患者197名に関して、死亡するまでの生物学的マーカーであるCRP値の推移を観察した。日常生活が困難になってから死亡するまでの日数は中央値26日であった。この時期に初めてエンド・オプ・ライフケアの話し合いが行われた割合は63%で、緩和ケアが提供された日数は19日であった。一方、CRP値は死亡6か月前に比べると3か月前の時点で有意に上昇が認められた。自立した日常生活を行うことが可能
な、死亡の3か月前の時点で、CRP値はすでに上昇している場合が多いことが判明した。エンド・オプ・ライフケアの話し合いを適切な時期に行うためには、生物学的マーカーが一つの客観的指標になりうると考えられる。
研究の目的と方法
生物学的マーカー(C-reactive protein値:以下CRP値およびアルプミン値:以下ALB値)が、人生終末期のケアの話し合いの時期を決定する指標になりうるかを検討した。
本研究の参加について
対象:2017年1月から2019年12月までの3年間に熊本医療センター腫瘍内科に入院したがん終末期患者197名。
研究により患者様に新たな検査や費用の負担が生じることはありません。また、研究に扱う情報は、個人が特定されない形で厳重に扱います。皆様の貴重な臨床データを使用させていただくことにご理解とご協力をお願いいたします。
本研究にご自身のデータを研究に使わないでほしいと希望されている方、その他研究に関してご質問がございます際は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。
調査する内容
方法:死亡からさかのぼって、どの時期に入院したのか、どの時期に終末期ケアに関する話し合いがなされ、どれだけの期間緩和ケアを受けたのかを観察した。また、死亡する1、2、3、6か月前の生物学的マーカーのCRP値とALB値の推移を観した。
調査期間
研究対象期間:平成29年 1月 1日~令和 1年 12月 31日まで
研究実施期間:倫理委員会承認後~令和6年12月 31日まで
研究成果の発表
論文投稿(日本緩和医療学会誌、他)
研究代表者
磯部 博隆
当院における研究責任者
磯部 博隆
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター腫瘍内科
〒860-0008熊本県熊本市中央区ニノ丸1-5
電話番号096-353-6501
169.アレルギー拠点病院ネットワークを活用したアナフィラキシー症例集積研究
国立病院機構熊本医療センターでは、下記の臨床研究を実施しております。この研究の計画、研究の方法についてお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ情報を利用することをご了解できない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。なお、この研究に参加している他の方の個人情報や、研究の知的財産等は、お答えできない内容もありますのでご了承ください。
研究の概要
アナフィラキシーとは、アレルギー症状が複数の臓器(肺や腸、心臓など)で出現し、生命の危機となる重篤な状態です。
日本では、どの様な患者さんがどの様な原因でアナフィラキシーを起こし、どの様な治療を受けたのかといった情報を全国から集めるシステムはありません。そのため、日本でのアナフィラキシーの誘因や治療、管理状況などがどのようになっているか十分に分かっていません。
研究の目的と方法
全国のアナフィラキシーの患者さんの情報を集めて、誘因・治療・管理状況の毎年の変化を調査し、各病院で情報を共有することにより、全国のアナフィラキシーの診断・治療・管理の向上を目的とします。
本研究の参加について
下記の研究期間内に、アナフィラキシーを発症し、発症から24時間以内に医師に診察された方
調査期間
院長承認後から2027年3月31日
利用するカルテ情報
患者背景(性別、年齢、過去のアナフィラキシーの原因と回数、事前のアドレナリン自己注射製剤の処方の有無)、今回のアナフィラキシーの経過(発症日、誘因、誘発症状、二相性反応の有無、7日以内の転機)、治療内容(アドレナリン自己注射製剤使用の有無、医療機関での治療内容、入院加療の有無、集中管理の有無)
情報の管理
上記の情報は、個人を特定する情報 (氏名、住所、診療録番号等)を削除して、個人を特定できないようにしたうえで研究代表者機関である国立病院機構相模原病院に郵送またはインターネットを介して提出され、集計、解析が行われます。
研究組織
この研究は、多施設との共同研究で行われます。研究で得られた情報は、共同研究機関内で利用されることがあります。
研究代表者(研究の全体の責任者)
国立病院機構相模原病院 臨床研究センター室長 佐藤さくら
その他の共同研究機関
慶応義塾大学 研究責任医師 足立 剛也
昭和大学 研究責任医師 鈴木 慎太郎
国立成育医療研究センター 研究責任医師 森田 英明、福家 辰樹
長野県立こども病院 研究責任医師 伊藤 靖典
国立病院機構三重病院 研究責任医師 長尾 みづほ
千葉大学医学部附属病院 研究責任医師 中野 泰至
福井大学医学部付属病院 研究責任医師 大嶋 勇成
あいち小児保健医療総合センター 研究責任医師 北村 勝誠
宮城県立こども病院 研究責任医師 三浦 克志
藤田医科大学 研究責任医師 矢上 晶子
[個人情報の取扱い]
研究に利用する情報には個人情報が含まれますが、院外に提出する場合には、お名前、住所など、個人を直ちに判別できる情報は削除し、研究用の番号を付けます。また、研究用の番号とあなたの名前を結び付ける対応表を当院の研究責任者が作成し、研究参加への同意の取り消し、診療情報との照合などの目的に使用します。対応表は、研究責任者が責任をもって適切に管理いたします。
情報は、当院の研究責任者及び情報の提供先である国立病院機構相模原病院が責任をもって適切に管理いたします。研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も個人を直ちに判別できるような情報は利用しません。
問い合わせ先
国立病院機構熊本医療センター 小児科 副部長 緒方美佳
電話 096-353-6501(代表) FAX 096-325-2519
168.クルミまたはカシューナッツアレルギー患者の発症および自然歴についての臨床的検討
当院では、国立病院機構相模原病院との共同研究として、下記の臨床研究を実施しております。この研究の計画、研究の方法についてお知りになりたい場合、この研究に検体やカルテ情報を利用することをご了解できない場合など、お問い合わせがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。なお、この研究に参加している他の方の個人情報や、研究の知的財産等は、お答えできない内容もありますのでご了承ください。
研究の概要
近年、木の実アレルギーが急増しており、日本では特にクルミアレルギーとカシューナッツアレルギーが多いです。重篤なアレルギー症状(アナフィラキシー)を起こしてしまう患者さんも少なくありません。また、海外では木の実アレルギーの発症に関する研究はいくつかありますが、日本ではまだ明らかではありません。そして、木の実アレルギーの患者さんのうちどれくらいの方がいつ頃耐性獲得(食物アレルギーが良くなり、食べられるようになること)するのか、耐性獲得に影響する要因についてはよく分かっていません。
本研究では、クルミアレルギーとカシューナッツアレルギー患者さんの発症時の臨床的情報(他のアレルギーの合併の有無、初めてのアレルギー症状がいつ・どのように起きたのかなど)と、耐性獲得の経過について調査をします。
研究の目的と方法
日本の小児のクルミまたはカシューナッツアレルギー患者さんの発症時の臨床的特徴と予後を明らかにすることです。
本研究の参加について
2013年1月1日から2025年3月31日までに参加施設に通院歴があり、即時型クルミまたはカシューナッツアレルギーと診断された患者様
調査期間
院長承認後から2025年3月31日
利用するカルテ情報
カルテ情報:患者背景(年齢、性別、生年月日、アレルギー疾患の既往、アレルギー疾患の家族歴)、初診日時、最終受診日時、発症前の経過、クルミまたはカシューナッツの摂取により即時型症状を初めて認めた時(=発症時)の経過(発生日時または年齢、場所、原因食品、症状、アナフィラキシーの有無)、クルミまたはカシューナッツアレルギー発症前の除去の有無、除去開始日時または年齢、除去を開始した理由、食物経口負荷試験の経過(実施日時または年齢、負荷量・摂取量、判定結果、症状、治療、再現性)、診断後の誤食の有無と経過(誤食した日時または年齢、その時の即時型症状の有無)、初めて感作を認めた時、発症時、診断後の血液検査(クルミまたはカシューナッツ特異的IgE値, Jug r 1またはAna o 3特異的IgE値,ハンノキ特異的IgE値、総IgE値)、日常生活でクルミまたはカシューナッツの摂取制限が不要になった日時または年齢、経口免疫療法実施の有無・開始時年齢
情報の管理
情報は、研究代表者機関である相模原病院にインターネットを介して匿名化、暗号化された状態で提出され、集計、解析が行われます。
[研究組織]
この研究は、多施設との共同研究で行われます。研究で得られた情報は、共同研究機関内で利用されることがあります。
研究代表者(研究の全体の責任者)
国立病院機構相模原病院 臨床研究センター 海老澤 元宏
[当院における研究責任者] 小児科 緒方 美佳
その他の共同研究機関
長野県立こども病院 アレルギー科 小池 由美
自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科 牧田 英士
茨城県立こども病院 小児科 貴達 俊徳
甲南医療センター 小児科 谷口 裕章
[個人情報の取扱い]
研究に利用する情報には個人情報が含まれますが、院外に提出する場合には、お名前、住所など、個人を直ちに判別できる情報は削除し、研究用の番号を付けます。また、研究用の番号とあなたの名前を結び付ける対応表を相模原病院の研究責任者が作成し、研究参加への同意の取り消し、診療情報との照合などの目的に使用します。対応表は、研究責任者が責任をもって適切に管理いたします。
情報は、相模原病院の研究責任者が責任をもって適切に管理いたします。研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も個人を直ちに判別できるような情報は利用しません。
[問い合わせ先]
国立病院機構熊本医療センター 小児科 緒方 美佳
電話 096-353-6501(代表) FAX 096-325-2519
167.重症敗血症性ショック患者の背景や治療実態、予後を観察する登録研究
研究の概要
様々な細菌やウイルスが人体を攻撃した結果として感染症が生じますが、感染症が悪くなってしまった状態を敗血症、さらに悪くなった状態を敗血症性ショックと呼びます。敗血症は死亡される方も多い重篤な状態であり早期目標指向型治療、免疫グロプリン療法、エンドトキシン(毒素)吸着療法など種々の治療が試みられていますが、単独で死亡率を低下させることが証明された治療法は現時点では明らかとなっていません。一方で、特に状態の悪い患者さんではこれらの治療の有効性が高い可能性が示されおり、より状態の悪い患者さんに協力いただく研究が必要と考えられています。そのため、重症の敗血症性ショックの患者さんを対象として種々の治療法の効果と予後との関連を解明するための研究を東北大学が中心となり、熊本医療センターでも実施することといたしました。
研究の目的
日本における敗血症性ショック患者に対する様々な治療実態を明らかにし、同時に患者背景や予後を評価することで、敗血症性ショック患者の有効な治療を探索することです。
研究の方法
診療内で測定するデータ、検査値を登録し、集積します。治療の実際とその成績を検討し、敗血症性ショック患者に有効な治療方法を見出し、検査や治療の実態を調査します。
調査する内容
この研究のための試料採取はいたしません。
情報として病歴、年齢、性別、治療に際して取得した血圧や脈拍の変化、採血検査の値などを使用します。
調査期間
研究対象期間:倫理委員会承認後~2022年12月
(登録症例例数が不足する場合には、2023年12月まで延長の可能性があります)
研究実施期間:倫理委員会承認後~2025年3月
研究成果の発表
研究代表者は、研究終了後、遅滞なく研究成果を医学雑誌などに公表します。
研究代表者
東北大学病院高度救命救急センター助教 佐藤哲哉
副研究責任者
兵庫医科大学臨床疫学 教授 森本剛
当院における研究責任者
救命救急センター長 櫻井聖大
問い合わせ先
櫻井聖大
熊本市中央区二の丸1-5
国立病院機構熊本医療センター
096·353-6501